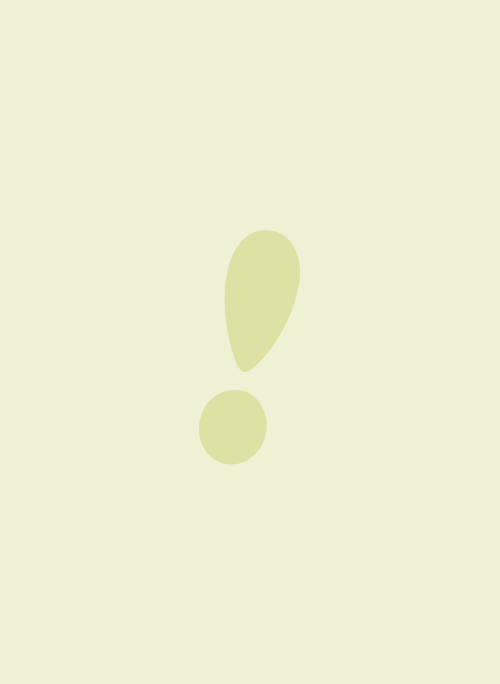幸枝は長津の提案で山梨への疎開が決まってからというもの、仕事や家のことを調整するのに急務ではないにしろ、どこか慌ただしいような気分で過ごしていた。神宮外苑へ行った日の二、三日後のことであるが、伊坂家の邸宅に妙な来訪者があった。
日夜を徹して働く男達の帰りは日に日に遅くなり、女だけの静まり返った斜陽に染まる邸宅の玄関に、ひとりの少女の声が響く。
「ごめんください」
幸枝は居間に居たが、二人の女中は炊事で手が離せないのか奥から出てくる気配は無い。ソファーを立った幸枝が玄関に出ると、目を腫らした少女が泣きじゃくりながらその場に立っていた。
「まあ、春子ちゃんじゃあないの。どうしたの」
昨秋会ったきりの二人であったが、軍需に応える伊坂家と軍需を生み出す陸軍の将官の松原家とはどこか立ち位置は近いもので、松原の娘は父から幸枝の話を聴いたのでよく知ったつもりでいた。
(「あいつの話はよしてくれよ」)
──対する幸枝は、春子の顔を見た瞬間、清士の力ない笑みが脳裏に蘇った。
春子は目を潤ませて、
「幸枝さん、私……」
と震えながら涙声を出している。
(流石に放っておくわけにはいかないわよね……?)
「とりあえず、お上がんなさいよ。私の部屋に案内してあげる」
幸枝は春子の手を取り、廊下の奥の階段を登る。
「特に出せるものがないけれど……お話ならいくらでも聞くわ」
二人は窓際のテーブルにつく。その間も少女は肩を小刻みに上下するように咽ぶような仕草を見せている。
「そんなに泣いてどうしたのよ」
春子の眼の周りは赤く腫れている。
日夜を徹して働く男達の帰りは日に日に遅くなり、女だけの静まり返った斜陽に染まる邸宅の玄関に、ひとりの少女の声が響く。
「ごめんください」
幸枝は居間に居たが、二人の女中は炊事で手が離せないのか奥から出てくる気配は無い。ソファーを立った幸枝が玄関に出ると、目を腫らした少女が泣きじゃくりながらその場に立っていた。
「まあ、春子ちゃんじゃあないの。どうしたの」
昨秋会ったきりの二人であったが、軍需に応える伊坂家と軍需を生み出す陸軍の将官の松原家とはどこか立ち位置は近いもので、松原の娘は父から幸枝の話を聴いたのでよく知ったつもりでいた。
(「あいつの話はよしてくれよ」)
──対する幸枝は、春子の顔を見た瞬間、清士の力ない笑みが脳裏に蘇った。
春子は目を潤ませて、
「幸枝さん、私……」
と震えながら涙声を出している。
(流石に放っておくわけにはいかないわよね……?)
「とりあえず、お上がんなさいよ。私の部屋に案内してあげる」
幸枝は春子の手を取り、廊下の奥の階段を登る。
「特に出せるものがないけれど……お話ならいくらでも聞くわ」
二人は窓際のテーブルにつく。その間も少女は肩を小刻みに上下するように咽ぶような仕草を見せている。
「そんなに泣いてどうしたのよ」
春子の眼の周りは赤く腫れている。