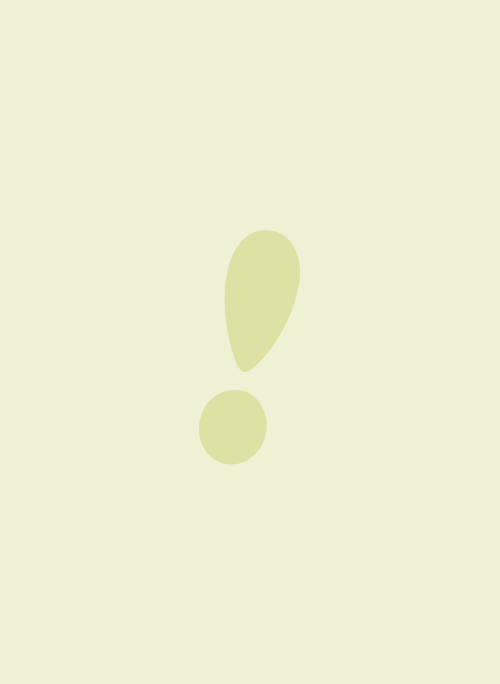真夏の昼下がりは燃えるような暑さである。
木々の真下は影になっており照りつける日光が遮られているが、頭上では蝉の声が鳴り響いており、その音を聴いているとたちまち蒸し返すような暑さに襲われる。
教育施設の立ち並ぶこの街は、駒場と呼ばれている。
幸枝の普段よりも濃い紅を差した唇からは、その麗しさと女性的な強さが際立っている。
暗い藍色のワンピースに包まれた身の胸元には向日葵を模ったブローチの山吹色が映えていた。
幸枝は、どうも落ち着かないという様子なのか、苛立っているのか、前のめりになって歩いている。
(どうして成田さんは私を呼びつけたのかしら、いや、呼びつけたというよりは、取り付けられたけれど)
公園で会った日から丁度一ヶ月と半月が立ったころ、清士は再び伊坂工業へ赴いた。
受付係に申し出て正面玄関へ降りてきた幸枝の表情は、不機嫌そのものであった。
「一体何の用かしら、今日も無駄に命乞いすることなく働いているわよ」
幸枝は学生にたっぷりの皮肉を浴びせる。
「この間は僕が悪かった……今度、近場で何処かに出掛けないかい。君の行きたい所なら何処でも」
清士のあまりの切り替えの速さに、
「何よ」
と幸枝は高らかに笑う。
清士は依然として申し訳なさそうな様子で、
「いや、あれから考えたんだ。君も相当大変な思いをして仕事に励んでいるのだと……だから、偶には息抜きなんてどうかと思ってね」
と提案した。
確かに、このところ幸枝は仕事詰で気が張り詰めていた。
折角この人も謝罪をして誘ってくれているのだからと、幸枝は一瞬迷った表情を見せながらも、
「良いわよ」
と返事をした。
木々の真下は影になっており照りつける日光が遮られているが、頭上では蝉の声が鳴り響いており、その音を聴いているとたちまち蒸し返すような暑さに襲われる。
教育施設の立ち並ぶこの街は、駒場と呼ばれている。
幸枝の普段よりも濃い紅を差した唇からは、その麗しさと女性的な強さが際立っている。
暗い藍色のワンピースに包まれた身の胸元には向日葵を模ったブローチの山吹色が映えていた。
幸枝は、どうも落ち着かないという様子なのか、苛立っているのか、前のめりになって歩いている。
(どうして成田さんは私を呼びつけたのかしら、いや、呼びつけたというよりは、取り付けられたけれど)
公園で会った日から丁度一ヶ月と半月が立ったころ、清士は再び伊坂工業へ赴いた。
受付係に申し出て正面玄関へ降りてきた幸枝の表情は、不機嫌そのものであった。
「一体何の用かしら、今日も無駄に命乞いすることなく働いているわよ」
幸枝は学生にたっぷりの皮肉を浴びせる。
「この間は僕が悪かった……今度、近場で何処かに出掛けないかい。君の行きたい所なら何処でも」
清士のあまりの切り替えの速さに、
「何よ」
と幸枝は高らかに笑う。
清士は依然として申し訳なさそうな様子で、
「いや、あれから考えたんだ。君も相当大変な思いをして仕事に励んでいるのだと……だから、偶には息抜きなんてどうかと思ってね」
と提案した。
確かに、このところ幸枝は仕事詰で気が張り詰めていた。
折角この人も謝罪をして誘ってくれているのだからと、幸枝は一瞬迷った表情を見せながらも、
「良いわよ」
と返事をした。