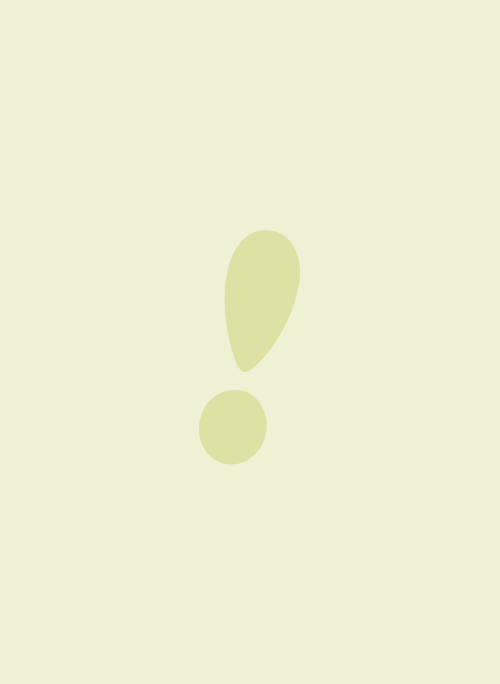それから幸枝と長津の「仕事」は毎月続いていたが、以前のように向かい合って座り話すことは無くなり、大抵は普段通り指定された場所で会い、挨拶すら交わさず、目にも付かない速さで封筒を手から手へと移動させたのち、何事もなかったように解散していくのであった。
長津は「仕事」の度に弁解の機会を窺っていたが、一方の幸枝は文字通り顔すら向けず、ひたと「仕事」をこなすのであった。
ある秋の日、年の暮れの近づく世間では鉄道旅客の抑制が始まった頃である。
北方と帝都を往来するこの駅も、些か人通りが減ったように思われた。
その日も例に漏れず指定の時間より五分早く到着した二人は、今度は伝言板の前に立ち、誰かの書き残した伝言を見るふりをしているうちに業務を終えていた。
小さな仕事相手は、封筒を受け取るとくるりと向きを変えて歩き出したが、今日ばかりは逃すまいと軍人もその姿を追いかける。
「伊坂さん」
呼び止める長津の声を跳ね除けるように、幸枝は早足で歩いていく。
しかし小柄な娘と図体の大きい軍人では話にならず、幸枝はすぐに追いつかれた。
「君は誤解している」
柔らかさを持たせたような声の中には、あの冷徹な低い音が入っている。
「私はこの任務を一任することを申し出たときに誓った、私がこの身を持って君を警護し、絶対に危険な事態には陥らせないと。この数ヶ月、私はこの一件に集中して任務を続けてきた。本来は私も外地に赴かなければならないが、この件があるのでまだ内地にいる。君に失礼のないように、物事が円滑に進むようにと、どんな任務よりも厳しい、細心の注意を払ってきたが、あの晩は冷静ではいられなかった。まずはそれを謝罪したい。そして翌日君が云ったように、私は確かに君を懐柔しようとした。しかし、それも愚かな方法であったと気が付いた。こうして誠意を持って依頼しなけらばならなかったと反省している。本当にすまなかった」
長津は「仕事」の度に弁解の機会を窺っていたが、一方の幸枝は文字通り顔すら向けず、ひたと「仕事」をこなすのであった。
ある秋の日、年の暮れの近づく世間では鉄道旅客の抑制が始まった頃である。
北方と帝都を往来するこの駅も、些か人通りが減ったように思われた。
その日も例に漏れず指定の時間より五分早く到着した二人は、今度は伝言板の前に立ち、誰かの書き残した伝言を見るふりをしているうちに業務を終えていた。
小さな仕事相手は、封筒を受け取るとくるりと向きを変えて歩き出したが、今日ばかりは逃すまいと軍人もその姿を追いかける。
「伊坂さん」
呼び止める長津の声を跳ね除けるように、幸枝は早足で歩いていく。
しかし小柄な娘と図体の大きい軍人では話にならず、幸枝はすぐに追いつかれた。
「君は誤解している」
柔らかさを持たせたような声の中には、あの冷徹な低い音が入っている。
「私はこの任務を一任することを申し出たときに誓った、私がこの身を持って君を警護し、絶対に危険な事態には陥らせないと。この数ヶ月、私はこの一件に集中して任務を続けてきた。本来は私も外地に赴かなければならないが、この件があるのでまだ内地にいる。君に失礼のないように、物事が円滑に進むようにと、どんな任務よりも厳しい、細心の注意を払ってきたが、あの晩は冷静ではいられなかった。まずはそれを謝罪したい。そして翌日君が云ったように、私は確かに君を懐柔しようとした。しかし、それも愚かな方法であったと気が付いた。こうして誠意を持って依頼しなけらばならなかったと反省している。本当にすまなかった」