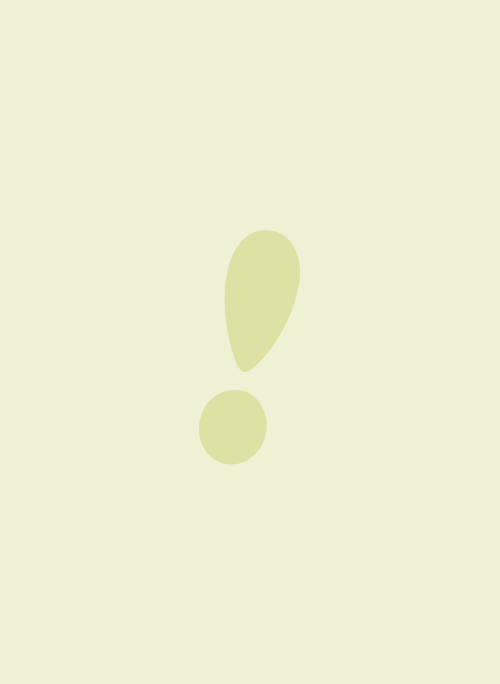目も眩むような盛夏の日。
朝から生温い風が吹き、立っているだけでも体内から汗が滲み出るような一日である。
正午ともなればその暑さは苛烈を極めていた。
「姉さん、お茶いる?」
夏季休暇の間小使として手伝いをすることになった昭二が小さな用紙を片手に各階の机を回る。
「昭二、私は確かに貴方の姉だけれど此処は会社よ。立場を弁えて頂戴」
「すみません」
ぺこりと頭を下げた弟に目もくれず、幸枝は額や首筋に汗を浮かべながらもタイプライターの鍵を打ち続けていた。
「お茶は如何ですか」
「ええ、頂くわ」
タイプライターの隣に置かれた麦茶の入ったコップには、瞬く間に水滴が浮かび始めている。
ひとつ書類を仕上げるごとに麦茶を飲むと、その冷たさが喉奥にまで染み渡る。
ただ途切れることなく打鍵とベルの音が鳴り響くこの部屋に、
「伊坂さん」
と幸枝を呼ぶ声が響いた。
「はい」
汗を拭いながら席を立った幸枝に一声掛けたのは、受付係の女性である。
「お客様がいらっしゃっておりますけれども」
「お客さん?私に?」
今日は何も約束は無い筈だと、突然の来客に首を傾げながらも受付係に促されて階下へ向かう。
「何方かしら」
「成田様という方です」
本社の入口に立つその人物を見た幸枝の表情が、暑さも忘れたかのような明るさになる。
「まあ!しばらく……」
白いシャツに身を包んだ大学生の涼しげな姿とその笑顔が眩しい。
「やあ」
幸枝は手拭いを畳みつつ清士を応接室に通した。
朝から生温い風が吹き、立っているだけでも体内から汗が滲み出るような一日である。
正午ともなればその暑さは苛烈を極めていた。
「姉さん、お茶いる?」
夏季休暇の間小使として手伝いをすることになった昭二が小さな用紙を片手に各階の机を回る。
「昭二、私は確かに貴方の姉だけれど此処は会社よ。立場を弁えて頂戴」
「すみません」
ぺこりと頭を下げた弟に目もくれず、幸枝は額や首筋に汗を浮かべながらもタイプライターの鍵を打ち続けていた。
「お茶は如何ですか」
「ええ、頂くわ」
タイプライターの隣に置かれた麦茶の入ったコップには、瞬く間に水滴が浮かび始めている。
ひとつ書類を仕上げるごとに麦茶を飲むと、その冷たさが喉奥にまで染み渡る。
ただ途切れることなく打鍵とベルの音が鳴り響くこの部屋に、
「伊坂さん」
と幸枝を呼ぶ声が響いた。
「はい」
汗を拭いながら席を立った幸枝に一声掛けたのは、受付係の女性である。
「お客様がいらっしゃっておりますけれども」
「お客さん?私に?」
今日は何も約束は無い筈だと、突然の来客に首を傾げながらも受付係に促されて階下へ向かう。
「何方かしら」
「成田様という方です」
本社の入口に立つその人物を見た幸枝の表情が、暑さも忘れたかのような明るさになる。
「まあ!しばらく……」
白いシャツに身を包んだ大学生の涼しげな姿とその笑顔が眩しい。
「やあ」
幸枝は手拭いを畳みつつ清士を応接室に通した。