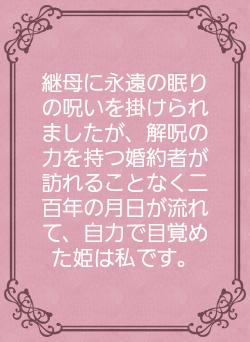ルイゼルトの影口を否定したい気持ちは山々だが、ここで出てしまったら最初から台無しになることは分かりきっていた。
ここは堪えるしかないと、踵を返して立ち去ろうとする。
「悪魔の妃か……どんな卑しい娘か見物だな」
「レゼルト王国は姫を犠牲にしてまで国を守るとは、中々面白い事を考えてくれますな」
「きっと姫も悪魔の使いか何かだろう。ここまで盛大なんだ、何かあってもおかしくはない」
「なんと。では、身の危険を感じたらそそくさと帰りましょうか」
豪快に笑う彼らの声は、しっかりとファウラの耳に届いた。自分を悪く言われるのには慣れきっているせいで、怒りすらも感じない。
馬鹿馬鹿しいと、今度こそ歩き出そうとしたが、彼らを制する一つの声がはっきりと聞こえた。
「言葉に気を遣われよ、大使方々。つまらない揶揄で身を滅ぼすのが趣味、というなら止めはしませんが」
「ロ、ロージャス公……」
落ち着いた静かな声だというのに、すぐ近くに居なくともルイゼルトを悪く言っていた者達が震えあがるのが分かる。