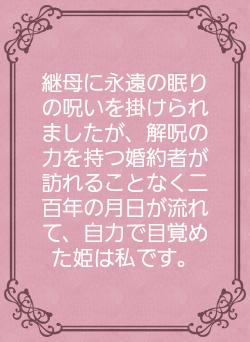だがファウラは、ルイゼルトの態度に臆することなくこれまで歩んできた道の事を話すことにした。
(陛下を知りたいと思っているのに、自分のことを話さないなんておかしな事だもの)
恐る恐るルイゼルトの瞳を覗くように見上げ、懐かしい記憶を優しく撫でるように話した。
「小さな馬小屋の隣の古い一軒家を改築したのが、私の家だった。日が昇ると同時に畑仕事をして、午後からは街の子供たちに勉強を教えたり、領主様から声が掛かればその補佐の手伝いもしていたの」
「でも、ファウラは一国の王女だろ?」
「一応王女としての肩書きはあるけど、十二の時に王宮から追い出された身なの。当てもない私を、とある領主の子息に手を差し出して貰えて、その街で恩返しするように過ごしてきた。でも体調を崩した姉の代わりに……と言えば聞こえはいいかもしれないけれど、最終的に捨て駒として二度目の追い出しを喰らってここに来たのよ」
「……」
一瞬黙ったルイゼルトだったが、愛おしむようにファウラの手を包み込んだ。
「馬鹿なレゼルトの国王に、一発ぶん殴りたい気持ちもあるが……捨て駒でもなんでもいい。俺は、ファウラと出会えた事に感謝したい。それにこんなじゃじゃ馬姫は、俺が乗りこなす方が丁度いいだろ」
「陛下……」
熱の籠った言い方に、きゅっと口を結ぶ。このまま我を忘れて、飲まれていきそうなギリギリなところで何とか耐え凌いだ。
「その街が好きだったように、きっとこの国も気に入る。これからは、この国がファウラの家になるんだからな」
握った手に力を込めて見えて来たぞと、ルイゼルトは窓の外に向かって視線を送った。その視線の先に広がる王都が、ゆっくりと近づいてくる。