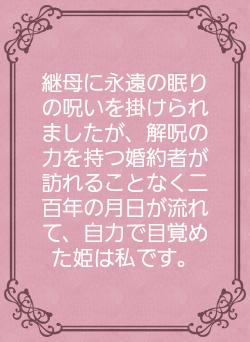これで断られたらどうしようと、焦りのあまりルイゼルトから手を放そうとするが、そうはさせないと強く握り締められた。
「安心しろ。俺は寧ろ……お前を手放すつもりはない」
ルイゼルトはそう呟くと、ファウラの腰に腕を回して膝に座らせた。
いきなり縮まった距離に赤面するファウラの耳元で、低い声が囁いてきた。
「知らない感情は、全部俺が教えてやる。だから――俺の傍に居ろ」
甘く囁かれたかと思えば、首筋に温かい何かが触れた。痺れる感覚に身動きが出来ないでいると、一度強く抱きしめられたかと思えば、すぐに解放された。
膝から降ろされ、名残り惜しむルイゼルトの手は、そっとファウラの髪に伸ばされる。長い髪の一房を唇に押し当てると、小さく笑った彼の笑顔に心臓が跳ねる。
「夜は冷える。もう寝ろ」
「……う、うん」
放された髪がふさりと一瞬頬に掛かる。残っているはずも無い、ルイゼルトの唇の感覚が髪を通して伝わってくるようで、うるさい程に心臓が鳴る。
ぎこちない動きのまま、部屋から出ようとドアノブに手を伸ばすと、後ろから優しい声が包み込んだ。
「おやすみ、ファウラ」
呼ばれた名前にまたしても胸が高鳴るのを誤魔化すように、おやすみと短く答えて部屋を出れば駆け足で部屋へと戻る。
ルイゼルトの執務室が見えなくなったところで、壁にもたれるようにして乱れる呼吸を何とか整えようと、深呼吸を繰り返す。だが、鳴り響く心音が、深呼吸をするファウラの邪魔をする。
(うるさい、うるさいっ……!何この心臓……どうやったら静かになるのよ)
何度深呼吸をしたところで、気持ちが落ち着く気配はなかった。
ルイゼルトが触れた場所が妙に熱い。夜は冷えると彼は言っていたが、ファウラの熱はいつまでも抜けることは無かった。