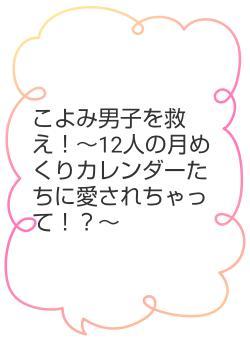スクールバックも、バイトの制服も、何もかも部屋に入るやいなやテキトーに落とすように置いた。
ラグマットの敷かれた床の上に座り、ベッドに顔を伏せて、どうしても止められなかった涙を流しながらお兄ちゃんに言われたことを考える。
暖房の無い私の部屋はひどく寒い。
確かにそうだ、約束を破ったのは私。
お兄ちゃんの言ってることは最もで正しい。
でもあんな…っ
バイトがダメだって決めつけられる意味もわかんないし、頭ごなしに全部否定しなくてもいいのに!私だって家のこと考えて、お兄ちゃんのこと考えて、私なりに…っ!
考えれば考えるほど、わかってくれないお兄ちゃんにモヤモヤするばかりで涙は止まらなかった。
悔しい、私が子供だからいけないの?
ーコンコン…っ
部屋のドアが2回叩かれた。
「芽衣…、ちょっといい?」
「…嫌だ」
今はお兄ちゃんの顔を見たくない。話をしたってわかってくれない。
「じゃあそのままでいいから。…芽衣がバイトしたい理由も聞いてないけど、俺がダメって言った理由も言ってなかったから、…聞いて」
「………。」
お兄ちゃんの声はいつも落ち着いている。それがすごく大人に思えて、私には絶対無理だって昔から思っていた。
「…心配だからだよ」
お兄ちゃんはすごいんだって、勝手に思ってた。
だって私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんで、私はいつだって妹でしかないから。
「高校生でバイトしてるやつなんてたくさんいるし、俺もしてたけど…うちには両親がいないから。俺も忙しくて芽衣が夜遅くなっても迎えには行ってやれないし、家にいればまぁ双子も、紘一さんたちもいるし…」
わかってくれないと思っていたお兄ちゃん、でもわかっていなかったのは私の方だったのかもしれない。
「そーゆう兄貴の気持ちもわかってよ」
たぶんお兄ちゃんは親がいない日向野家で誰より気を張っていたんだ。
子供の私にはそれがちゃんと理解できてなくて、気付けなかった。
「芽衣の気持ちもわかってなかったけど。…俺に言いたいことないの?」
だけどやっぱり私は子供だから、お兄ちゃんみたいにはできないの。
泣きじゃくった顔でゆっくり部屋のドアを開けた。
お兄ちゃんが困ったように笑っていた。
「さみしい~~~~~!!!」
「泣き過ぎだろっ!笑」
ぽろぽろと涙を流す私の頬をお兄ちゃんが両手でつかんだ。
「泣いたらブスになるからせめて笑っとけ!」
「ひどっ」
お兄ちゃんの手は私なんかより全然大きくて、これがお兄ちゃんなんだなって…あたりまえだけどそう感じた。
安心出来る、優しい手。
ラグマットの敷かれた床の上に座り、ベッドに顔を伏せて、どうしても止められなかった涙を流しながらお兄ちゃんに言われたことを考える。
暖房の無い私の部屋はひどく寒い。
確かにそうだ、約束を破ったのは私。
お兄ちゃんの言ってることは最もで正しい。
でもあんな…っ
バイトがダメだって決めつけられる意味もわかんないし、頭ごなしに全部否定しなくてもいいのに!私だって家のこと考えて、お兄ちゃんのこと考えて、私なりに…っ!
考えれば考えるほど、わかってくれないお兄ちゃんにモヤモヤするばかりで涙は止まらなかった。
悔しい、私が子供だからいけないの?
ーコンコン…っ
部屋のドアが2回叩かれた。
「芽衣…、ちょっといい?」
「…嫌だ」
今はお兄ちゃんの顔を見たくない。話をしたってわかってくれない。
「じゃあそのままでいいから。…芽衣がバイトしたい理由も聞いてないけど、俺がダメって言った理由も言ってなかったから、…聞いて」
「………。」
お兄ちゃんの声はいつも落ち着いている。それがすごく大人に思えて、私には絶対無理だって昔から思っていた。
「…心配だからだよ」
お兄ちゃんはすごいんだって、勝手に思ってた。
だって私にとってお兄ちゃんはお兄ちゃんで、私はいつだって妹でしかないから。
「高校生でバイトしてるやつなんてたくさんいるし、俺もしてたけど…うちには両親がいないから。俺も忙しくて芽衣が夜遅くなっても迎えには行ってやれないし、家にいればまぁ双子も、紘一さんたちもいるし…」
わかってくれないと思っていたお兄ちゃん、でもわかっていなかったのは私の方だったのかもしれない。
「そーゆう兄貴の気持ちもわかってよ」
たぶんお兄ちゃんは親がいない日向野家で誰より気を張っていたんだ。
子供の私にはそれがちゃんと理解できてなくて、気付けなかった。
「芽衣の気持ちもわかってなかったけど。…俺に言いたいことないの?」
だけどやっぱり私は子供だから、お兄ちゃんみたいにはできないの。
泣きじゃくった顔でゆっくり部屋のドアを開けた。
お兄ちゃんが困ったように笑っていた。
「さみしい~~~~~!!!」
「泣き過ぎだろっ!笑」
ぽろぽろと涙を流す私の頬をお兄ちゃんが両手でつかんだ。
「泣いたらブスになるからせめて笑っとけ!」
「ひどっ」
お兄ちゃんの手は私なんかより全然大きくて、これがお兄ちゃんなんだなって…あたりまえだけどそう感じた。
安心出来る、優しい手。