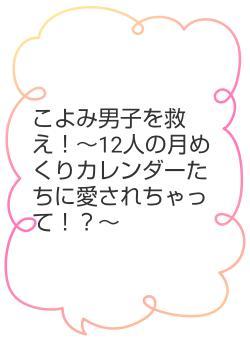芽衣に手を振って家に入った。
「おかえり」
「あー、ただいま」
出掛けようとしていた結華ねぇーちゃんが玄関に座り、ブーツの紐を結んでいた。長い髪をくるんくるんに巻いていつになく気合が入っている。
「お父さんが買って来てくれたイタリアのチョコレートあるよ。もうあんたの分だけだから」
「今度はイタリアかよ」
「でもめっちゃくちゃ美味しかったわよ」
靴を脱いで結華ねぇーちゃんの横を通り過ぎるように家の中に入った。
「本当よく買ってくるよなー、毎回大量に」
多忙なとーちゃんは日本だけじゃなく海外出張も多い。その時は必ずおみやげを買って来る。
「家族多いからね、1人1個は必須でしょ!」
「…絶対に1人1個あるんだよな」
もちろんみんなそれを楽しみに待ってるんだけど。
「そうね、ケンカするからね」
紐を縛り終わった結華ねぇーちゃんが玄関に置いたバッグを持った。とんとんっと靴を慣らして髪を掻き上げる。
「じゃあ行ってくるから」
ねぇーちゃんに背を向けたままゆっくり口を開いた。
「…あいつは?」
「え?大志?帰って来たけど、また出掛けてったわよ」
「そっか…」
「うん」
外に出ようと結華ねぇーちゃんがドアノブに手をかけた。
「あいつさ!」
「ん?」
でもちょっと聞いてほしくて、引き留めるように背を向けたまま声を大きくした。
「とーちゃんのおみやげとか、好きなくせに、絶対とっておく癖があってさ」
「うん」
「それどーすんの?って聞いたら、…芽衣にあげるんだって」
とーちゃんが買って来たチョコレートとかプリンとかクッキーとか…
なんなら芽衣には別に用意されていても、昔からそうだった。
「芽衣はたいして好きじゃねぇのに」
「そうね…」
「…でも、笑うから」
全然好きじゃないクッキーもらった時も、絶対食わない饅頭もらった時も、可愛いだけのマカロンもらった時も嬉しそうに笑うんだ…芽衣は。
「その顔が見たかっただけなんだろうな」
「大志は単純だからね」
「…もし、俺が同じことをしてたら芽衣はどうしたかな?」
そのあと芽衣は半分こしようって、大志に半分渡すんだ。
それが無性に羨ましかった。
あんなに物足りないって思ってたのに。
「笑うんじゃない?」
穏やかで明るいねぇーちゃんの声、妙に落ち着いた。
「あんたたちのこと同じだとも思ってなかったけど、差別だってしたことなかったじゃない。ちゃんと、それぞれのこと見てたわよ」
「………。」
「…そーゆうとこが好きだったんでしょ?」
「………うん」
「じゃあ、私出掛けるから!みんなに言っといて!」
ガチャン、とドアの閉まる音がした。
その瞬間つーっと一滴、瞳から涙が流れた。
ずっと見てたからわかっていた。
芽衣が大志のことを見ていることは。
これだけ長い間隣にいたんだ、気付かないはずなくて…
全部わかっていた、こうなることも。
だから、先に言いたかった。
困らせたかったわけでもなくて、関係を壊したいわけでもなくて、ただ大切だなけだった。
俺もあの笑顔を見ていたかった。
それだけだったんだ。
「おかえり」
「あー、ただいま」
出掛けようとしていた結華ねぇーちゃんが玄関に座り、ブーツの紐を結んでいた。長い髪をくるんくるんに巻いていつになく気合が入っている。
「お父さんが買って来てくれたイタリアのチョコレートあるよ。もうあんたの分だけだから」
「今度はイタリアかよ」
「でもめっちゃくちゃ美味しかったわよ」
靴を脱いで結華ねぇーちゃんの横を通り過ぎるように家の中に入った。
「本当よく買ってくるよなー、毎回大量に」
多忙なとーちゃんは日本だけじゃなく海外出張も多い。その時は必ずおみやげを買って来る。
「家族多いからね、1人1個は必須でしょ!」
「…絶対に1人1個あるんだよな」
もちろんみんなそれを楽しみに待ってるんだけど。
「そうね、ケンカするからね」
紐を縛り終わった結華ねぇーちゃんが玄関に置いたバッグを持った。とんとんっと靴を慣らして髪を掻き上げる。
「じゃあ行ってくるから」
ねぇーちゃんに背を向けたままゆっくり口を開いた。
「…あいつは?」
「え?大志?帰って来たけど、また出掛けてったわよ」
「そっか…」
「うん」
外に出ようと結華ねぇーちゃんがドアノブに手をかけた。
「あいつさ!」
「ん?」
でもちょっと聞いてほしくて、引き留めるように背を向けたまま声を大きくした。
「とーちゃんのおみやげとか、好きなくせに、絶対とっておく癖があってさ」
「うん」
「それどーすんの?って聞いたら、…芽衣にあげるんだって」
とーちゃんが買って来たチョコレートとかプリンとかクッキーとか…
なんなら芽衣には別に用意されていても、昔からそうだった。
「芽衣はたいして好きじゃねぇのに」
「そうね…」
「…でも、笑うから」
全然好きじゃないクッキーもらった時も、絶対食わない饅頭もらった時も、可愛いだけのマカロンもらった時も嬉しそうに笑うんだ…芽衣は。
「その顔が見たかっただけなんだろうな」
「大志は単純だからね」
「…もし、俺が同じことをしてたら芽衣はどうしたかな?」
そのあと芽衣は半分こしようって、大志に半分渡すんだ。
それが無性に羨ましかった。
あんなに物足りないって思ってたのに。
「笑うんじゃない?」
穏やかで明るいねぇーちゃんの声、妙に落ち着いた。
「あんたたちのこと同じだとも思ってなかったけど、差別だってしたことなかったじゃない。ちゃんと、それぞれのこと見てたわよ」
「………。」
「…そーゆうとこが好きだったんでしょ?」
「………うん」
「じゃあ、私出掛けるから!みんなに言っといて!」
ガチャン、とドアの閉まる音がした。
その瞬間つーっと一滴、瞳から涙が流れた。
ずっと見てたからわかっていた。
芽衣が大志のことを見ていることは。
これだけ長い間隣にいたんだ、気付かないはずなくて…
全部わかっていた、こうなることも。
だから、先に言いたかった。
困らせたかったわけでもなくて、関係を壊したいわけでもなくて、ただ大切だなけだった。
俺もあの笑顔を見ていたかった。
それだけだったんだ。