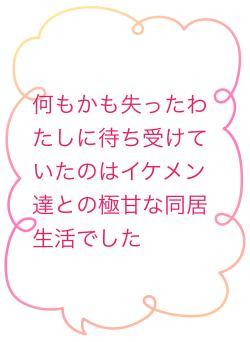そんなわたしの腰を王子は片腕だけで支えて尚も止まらないキス、キス、キス。
酸欠と身体の神経までも麻痺するような痺れる熱い感覚に、意識を保つことだけで精一杯。
やっと解放されたと思ったのも束の間、立っていることも出来なくなったわたしを抱きかかえ王子はそっとベッドへと運び、そんなわたしの上に覆い被さる形になった。
「おう…じ。や、め、」
「あまね」
「…?」
「あまねって言ってくれたら、これ以上のことはしない。約束したしね」
「あま、ね、」
「これからは王子じゃなくてそう呼んで?次から王子って呼んだら公衆の面前でキスするから」
わたしがそういうことされるの嫌なの知ってて言っているな。くそぅ。
でも、はむかえない。
「うう…わかった」
「武石が入る余地もないぐらい凛々のこと夢中にさせるから」
最後にもう一度わたしにキスを落として、おう…天音は満足したのか機嫌良く帰っていった。
わたしは放心状態でベッドから起き上がることも出来ないまま。
…な、なんなんだ。何だと言うんだいったい。
天音にしても武石先生にしても、なんだってわたしを…
とにかく頭の中がぐちゃぐちゃで、この日は一睡も出来ないまま朝を迎えたのだった。