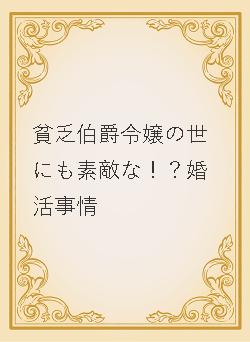「ルーカス……私には、ルーカス達獣人のいう〝番〟が、やっぱりよくわからないの。獣人に生まれたがための、抗えない本能じゃないの?相手の中身なんて関係なくて、匂いで惹かれてしまった。そういうことじゃないの?」
その疑問は、確かに私の中にあった。けれど、ずっと自分の内に秘めてきたものだ。
彼が今、悔しく思っていることや、呪いを解くことを私に求めてくることのプレッシャー。申し訳ない気持ちとか、自分でも説明できないような複雑な思いから、つい口にしてしまった。
ルーカスは静かに立ち上がると、そっと私の横に座り直した。机に乗せていた私の手を取って、優しく包み込んでくれる。
「ライラ、確かに獣人は番の匂いに抗えない。それは事実だから否定しない」
ルーカスは、本当のことを話してくれている。それだけに、胸の奥がチクチクと痛むのは、もう気のせいだなんて言えそうにない。匂いだけで私を求めているという事実が、たまらなく悲しかった。
「でも、それだけじゃないんだ。匂いに惹かれるということは、相手の本質を本能で察知して、その全てに惹かれるということなんだ。それはもう、獣人だからわかる感覚だな。そうだなあ……人間の女性が、好みの香りの香水を欲しがるのとはわけが違う。匂いは、その人の全ての情報が詰まってるんだ」
真剣に見つめるルーカスを、同じように見返す。
「想像してみてよ。番は匂いありきじゃない。自分にとって、性格も価値観も全て好ましい人物だからこそ、自分の惹かれる匂いがするんだ。獣人が一生たった一人を想うのは、相手が番だからじゃない。全てにおいて惹かれる相手だからだ。それが番なんだ」
これ以上、〝でも……〟なんて言い返そうとは思えなかった。
ますます俯く私の手をそっと握り直したルーカスは、優しい声音で続ける。
その疑問は、確かに私の中にあった。けれど、ずっと自分の内に秘めてきたものだ。
彼が今、悔しく思っていることや、呪いを解くことを私に求めてくることのプレッシャー。申し訳ない気持ちとか、自分でも説明できないような複雑な思いから、つい口にしてしまった。
ルーカスは静かに立ち上がると、そっと私の横に座り直した。机に乗せていた私の手を取って、優しく包み込んでくれる。
「ライラ、確かに獣人は番の匂いに抗えない。それは事実だから否定しない」
ルーカスは、本当のことを話してくれている。それだけに、胸の奥がチクチクと痛むのは、もう気のせいだなんて言えそうにない。匂いだけで私を求めているという事実が、たまらなく悲しかった。
「でも、それだけじゃないんだ。匂いに惹かれるということは、相手の本質を本能で察知して、その全てに惹かれるということなんだ。それはもう、獣人だからわかる感覚だな。そうだなあ……人間の女性が、好みの香りの香水を欲しがるのとはわけが違う。匂いは、その人の全ての情報が詰まってるんだ」
真剣に見つめるルーカスを、同じように見返す。
「想像してみてよ。番は匂いありきじゃない。自分にとって、性格も価値観も全て好ましい人物だからこそ、自分の惹かれる匂いがするんだ。獣人が一生たった一人を想うのは、相手が番だからじゃない。全てにおいて惹かれる相手だからだ。それが番なんだ」
これ以上、〝でも……〟なんて言い返そうとは思えなかった。
ますます俯く私の手をそっと握り直したルーカスは、優しい声音で続ける。