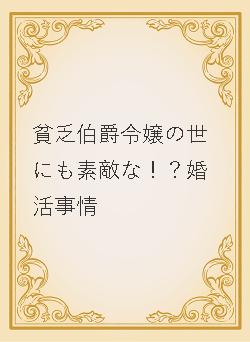いつになく言葉の少ないルーカスに、ちらりと目を向ける。なにか思い詰めたように、眉間に皺を寄せて一点を睨むようにしているルーカスに、胸がチクチクと痛んだ。
本当なら、ルーカス自身が先陣を切って外へ向かいたいはず。けれど、今のルーカスにはそれができない。
たとえ今晴れていて、カエルになってしまう心配がなかったとしても、彼はここに留まるしかないのだろうか?
あの呪いが、ルーカスにとってどれほど大きな足枷になっているのだろう?
もし出先で突然の雨に降られたら?
その時、一人でいたら?
カエルになってしまえば、無防備すぎて命の危険だってあり得る。
今私が感じているこの胸の痛みや、妙な焦りみたいなものは、ルーカスを憐れんでのものなのだろうか?私は彼に同情してる?だとしたら、なんて傲慢なのだろう。
彼はカエルの呪いに苛立ってはいても、決して呪いを解くことを諦めてはいないのに……
ぐちゃぐちゃになった思考を散らすように、小さく首を振った。
「ライラ」
すっかり考え込んでいたら、ふとルーカスが声をかけてきた。
「ん?」
「今、ライラはいま、なにを考えていたんだ?」
「なにって……いろいろと……」
俯く私の頬に、そっと大きな手が当てられる。その温かさに、ドキリと胸が跳ねた。なんだかいつもと勝手が違って、振り払うことも軽く流すこともできそうにない。妙な気まずさというか……
だんだんと、自分の顔が熱くなっていくのがわかる。それをルーカスに気付かれたくなくて、顔を上げることができない。
「自分の番が一人で悩んでいるなんて、俺には見過ごすことができない。番の悩みや不安は、いつだって共有したい。助けになりたいんだ」
番、番っていうけれど、そんなの匂いで判断してるだけじゃないの?相手がどんな人物だったとしても、その匂いに惹かれてしまえば、もう一生抗うことができなくなってしまう。そんなの、相手の本質を好きになったとはいえない。
本当なら、ルーカス自身が先陣を切って外へ向かいたいはず。けれど、今のルーカスにはそれができない。
たとえ今晴れていて、カエルになってしまう心配がなかったとしても、彼はここに留まるしかないのだろうか?
あの呪いが、ルーカスにとってどれほど大きな足枷になっているのだろう?
もし出先で突然の雨に降られたら?
その時、一人でいたら?
カエルになってしまえば、無防備すぎて命の危険だってあり得る。
今私が感じているこの胸の痛みや、妙な焦りみたいなものは、ルーカスを憐れんでのものなのだろうか?私は彼に同情してる?だとしたら、なんて傲慢なのだろう。
彼はカエルの呪いに苛立ってはいても、決して呪いを解くことを諦めてはいないのに……
ぐちゃぐちゃになった思考を散らすように、小さく首を振った。
「ライラ」
すっかり考え込んでいたら、ふとルーカスが声をかけてきた。
「ん?」
「今、ライラはいま、なにを考えていたんだ?」
「なにって……いろいろと……」
俯く私の頬に、そっと大きな手が当てられる。その温かさに、ドキリと胸が跳ねた。なんだかいつもと勝手が違って、振り払うことも軽く流すこともできそうにない。妙な気まずさというか……
だんだんと、自分の顔が熱くなっていくのがわかる。それをルーカスに気付かれたくなくて、顔を上げることができない。
「自分の番が一人で悩んでいるなんて、俺には見過ごすことができない。番の悩みや不安は、いつだって共有したい。助けになりたいんだ」
番、番っていうけれど、そんなの匂いで判断してるだけじゃないの?相手がどんな人物だったとしても、その匂いに惹かれてしまえば、もう一生抗うことができなくなってしまう。そんなの、相手の本質を好きになったとはいえない。