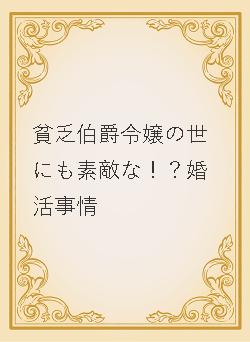改めて、目の前の幼馴染を見つめる。
「ヴィンセント……」
「セシリア!!あぁ、今はライラだったな?殿下から聞いてる」
「う、うん」
「元気にしてたか?」
「ええ。見ての通りよ」
「よかった……」
再び私を抱きしめるヴィンセントに、羽交い締めにされているルーカスが盛大に喚く。が、無視だ、無視。
「ずっと心配してた」
「ごめん。あれから、連絡の一つもしないで」
「そうだな。けど、アルフレッド殿下から、少し前に聞いてたから」
ヴィンセントは私の現状を確かめるように、じっと顔を覗き込んでくる。その表情に、ずいぶん心配をかけてしまったことが伺えて、申し訳なくなってくる。
「てっきり、サンミリガンへ行ったと思ってたけど……」
ぐるりと店内を見回したヴィンセントは、ルーカスに視線をとめた。
「意外と近くにいたんだな。すっかり新しい生活も馴染んでて。わけのわからんヤツもいるけど」
「ははは。まあ、あの人は気にしないで」
「わけがわからんとは、失礼だぞ。俺はそこにいるライラの番だ!!」
「番?」
ヴィンセントが不思議そうに呟いた。が、まだなにかあったようで、アルフレッドが口を挟む。
「ライラ。それはともかく、連れてきたのは彼だけじゃない。そろそろ呼びに行きたいのだが」
「殿下、私が連れて参ります」
「ああ頼んだ」
どうやら、小型の馬車で乗り付けていたようだ。次にヴィンセントが連れてきた人物に、思わず目を見開いた。言葉なんて一つも出てこない。代わりに、幾筋もの涙が頬を伝った。
さっきまで騒いでいたルーカスも、流石になにかを察してのか、居合わせた他の人同様に、口をつぐんで私と客人を見ていた。
「ヴィンセント……」
「セシリア!!あぁ、今はライラだったな?殿下から聞いてる」
「う、うん」
「元気にしてたか?」
「ええ。見ての通りよ」
「よかった……」
再び私を抱きしめるヴィンセントに、羽交い締めにされているルーカスが盛大に喚く。が、無視だ、無視。
「ずっと心配してた」
「ごめん。あれから、連絡の一つもしないで」
「そうだな。けど、アルフレッド殿下から、少し前に聞いてたから」
ヴィンセントは私の現状を確かめるように、じっと顔を覗き込んでくる。その表情に、ずいぶん心配をかけてしまったことが伺えて、申し訳なくなってくる。
「てっきり、サンミリガンへ行ったと思ってたけど……」
ぐるりと店内を見回したヴィンセントは、ルーカスに視線をとめた。
「意外と近くにいたんだな。すっかり新しい生活も馴染んでて。わけのわからんヤツもいるけど」
「ははは。まあ、あの人は気にしないで」
「わけがわからんとは、失礼だぞ。俺はそこにいるライラの番だ!!」
「番?」
ヴィンセントが不思議そうに呟いた。が、まだなにかあったようで、アルフレッドが口を挟む。
「ライラ。それはともかく、連れてきたのは彼だけじゃない。そろそろ呼びに行きたいのだが」
「殿下、私が連れて参ります」
「ああ頼んだ」
どうやら、小型の馬車で乗り付けていたようだ。次にヴィンセントが連れてきた人物に、思わず目を見開いた。言葉なんて一つも出てこない。代わりに、幾筋もの涙が頬を伝った。
さっきまで騒いでいたルーカスも、流石になにかを察してのか、居合わせた他の人同様に、口をつぐんで私と客人を見ていた。