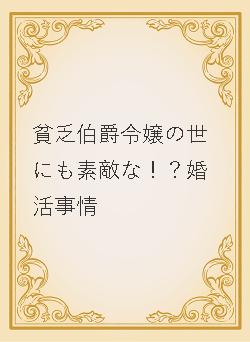「ライラ。陛下に尋ねてみたが、交流のある国の中で、マリアーナという名の王女のいた国に、心当たりはないようだ。とはいえ、ライラの話だと、マリアーナは王女として表舞台に立つことはなかったようだ。王女の存在を知らされていないだけで、実は知っている国かもしれないが」
「そうよね……対外的に、王女の存在をオープンにしていない可能性は十分にあるわ」
アルフレッドは、陛下の他にも尋ねてくれたようだけど、予想していた通り、手がかりは得られなかったようだ。
「本来なら……もっと早くに話すべきだっんだが……」
他にも話があったようで、アルフレッドに促されて、宿屋の彼の執務室へ入った。今日は側近も詰めていた。
「セシリア……君がセシリアだということを認めないというのなら、それでもかまわない。私の過去を知っている前提で話をしたい」
セシリアとして……明確には認めない。けれど、アルフレッドの話はちゃんと聞くことにした。
「私がセシリアと婚約破棄してしばらくした頃、彼女の幼馴染という騎士が、私の元へやってきた。いや、直訴しにきたというべきかな。王太子である私に、ずいぶん失礼な態度だったな。ちょうどその時、自分の下した判断に疑念を抱きはじめた頃で、彼の……ヴィンセントの言うことには、ハッとさせられた」
ヴィンセント……
幼少期を共に過ごした、私の幼馴染。私が家を出ると決めた時、ここまで来る手助けをしてくれた人物だ。
「どうしてセシリアの言葉を信じようとしなかったのかと。彼もまた、セシリアに想いを寄せていたのだろうな。私の知らなかったセシリアのことを、たくさん話してくれた。そして、姿を消したことも聞かされた。
愚かだった。もう少し周りに耳を傾けて、彼女と向き合う勇気と冷静さを持てていたのなら、こうはならなかったはず。私が唯一愛した彼女と、今頃幸せな新婚生活を過ごしていたことだろう。過ぎたことを悔いても仕方がないとわかってはいても、そう思わずにはいられないのだ」
彼がここへ来て以来、なんだか前向きな発言もしていたけれど、心の奥底にはまだ過去の出来事が燻っているようだ。こうしてここへ……私の元へ通い、多くの時間を過ごしているのは、もしかしたらセシリアを追い求めているというより、懺悔の気持ちが大きいのかもしれない。そのことに、彼自身が気付いているかはわからないけれど。
「そうよね……対外的に、王女の存在をオープンにしていない可能性は十分にあるわ」
アルフレッドは、陛下の他にも尋ねてくれたようだけど、予想していた通り、手がかりは得られなかったようだ。
「本来なら……もっと早くに話すべきだっんだが……」
他にも話があったようで、アルフレッドに促されて、宿屋の彼の執務室へ入った。今日は側近も詰めていた。
「セシリア……君がセシリアだということを認めないというのなら、それでもかまわない。私の過去を知っている前提で話をしたい」
セシリアとして……明確には認めない。けれど、アルフレッドの話はちゃんと聞くことにした。
「私がセシリアと婚約破棄してしばらくした頃、彼女の幼馴染という騎士が、私の元へやってきた。いや、直訴しにきたというべきかな。王太子である私に、ずいぶん失礼な態度だったな。ちょうどその時、自分の下した判断に疑念を抱きはじめた頃で、彼の……ヴィンセントの言うことには、ハッとさせられた」
ヴィンセント……
幼少期を共に過ごした、私の幼馴染。私が家を出ると決めた時、ここまで来る手助けをしてくれた人物だ。
「どうしてセシリアの言葉を信じようとしなかったのかと。彼もまた、セシリアに想いを寄せていたのだろうな。私の知らなかったセシリアのことを、たくさん話してくれた。そして、姿を消したことも聞かされた。
愚かだった。もう少し周りに耳を傾けて、彼女と向き合う勇気と冷静さを持てていたのなら、こうはならなかったはず。私が唯一愛した彼女と、今頃幸せな新婚生活を過ごしていたことだろう。過ぎたことを悔いても仕方がないとわかってはいても、そう思わずにはいられないのだ」
彼がここへ来て以来、なんだか前向きな発言もしていたけれど、心の奥底にはまだ過去の出来事が燻っているようだ。こうしてここへ……私の元へ通い、多くの時間を過ごしているのは、もしかしたらセシリアを追い求めているというより、懺悔の気持ちが大きいのかもしれない。そのことに、彼自身が気付いているかはわからないけれど。