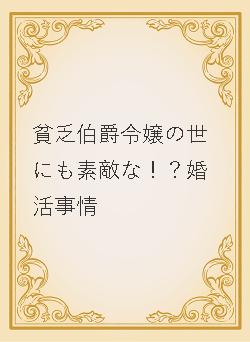「国によって違うだろうから、なんとも言えないが……グリージアでいえば、完全なる一夫一妻制の国だ。陛下も王妃も、それぞれに寝室があるとはいえ、基本的には毎晩2人の寝室で過ごしているはず。別々に過ごす時は、侍女や侍従が隣室に控えている上、ドアの外には必ず護衛がついている。だから、不貞など働く隙はない。たとえ一夫多妻制の国であっても、国王が毎晩誰の元を訪れたか、それから王妃や側妃が自室で過ごしたかという動向は、全て管理されていることが多いんじゃないか?国王の地位に目が眩んで、それこそ不義の子を陛下の子だと偽らないとも限らないからな」
えっと……王族って、なかなか窮屈なのね。なんとなくわかってはいたけれど、プライベートなんて皆無だ。
でも、そうせざるを得なくなったのには、それなりの歴史があるのだろう。地位や名誉に目が眩んでしまうなんて、よくある話だから。
「人間って、なかなか面倒な種族なんだな」
「どういうこと?」
ぽつりと呟いたルーカスを見やる。オオカミの獣人である彼にしたら、感覚が違うというのだろうか?
「獣人はこの人だと番を見つけたら、もう他の異性なんて一切目に入らない。一生のうちで想うのは、たった1人だけ。妥協なんてないし、ましてよそ見なんて。しようと考えることすらない。それは、身分に関係なくだ」
そういえば、以前ここで働いていたウサギの獣人のチェリーもそんなことを話していた。特定の1人、〝番〟を探し求める獣人は、その唯一の異性としか番えないのだと。出会えなかったり、受け入れてもらえなかったりしても、それじゃあ別の人にとはならないらしい。
「だから、不貞など考えられない。たとえ番が人間だったとしても、獣人は自分の持てる全てで相手を愛し、包み込んで、自分だけを見てくれるように尽くす。万が一、番となった人間が不貞を働けば、獣人の優れた嗅覚でわかってしまうしな」
「見張る必要がないってことか」
「ああ、そうだ」
えっと……王族って、なかなか窮屈なのね。なんとなくわかってはいたけれど、プライベートなんて皆無だ。
でも、そうせざるを得なくなったのには、それなりの歴史があるのだろう。地位や名誉に目が眩んでしまうなんて、よくある話だから。
「人間って、なかなか面倒な種族なんだな」
「どういうこと?」
ぽつりと呟いたルーカスを見やる。オオカミの獣人である彼にしたら、感覚が違うというのだろうか?
「獣人はこの人だと番を見つけたら、もう他の異性なんて一切目に入らない。一生のうちで想うのは、たった1人だけ。妥協なんてないし、ましてよそ見なんて。しようと考えることすらない。それは、身分に関係なくだ」
そういえば、以前ここで働いていたウサギの獣人のチェリーもそんなことを話していた。特定の1人、〝番〟を探し求める獣人は、その唯一の異性としか番えないのだと。出会えなかったり、受け入れてもらえなかったりしても、それじゃあ別の人にとはならないらしい。
「だから、不貞など考えられない。たとえ番が人間だったとしても、獣人は自分の持てる全てで相手を愛し、包み込んで、自分だけを見てくれるように尽くす。万が一、番となった人間が不貞を働けば、獣人の優れた嗅覚でわかってしまうしな」
「見張る必要がないってことか」
「ああ、そうだ」