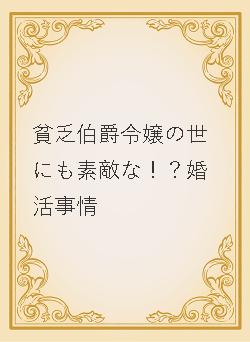「獣人同士の番だって同じだ。本能で惹かれ合うから番う。でも、それだけじゃない。想う相手が少しでも嫌な思いをしないように、今以上に幸せを感じられるように、獣人同士の番でも尽くし合うことを怠らない。
なあ、ライラ。同じじゃないか?相手が人間であろうと獣人であろうと、愛しい相手に尽くし合う。そういうことだろ?」
愛しい相手に尽くし合う……
ルーカスを苦しめないために、自分にできることを探す。今の私は、まさしく彼の言う通りなのかもしれない。そして、ルーカスが私にしてくれる全ての行動も、言葉も、また同じこと。
「そうね。その通りだわ」
ルーカスの話が、ストンと胸に落ちた。
「ルーカス」
その名を呼べば、私を見つめ続けていた瞳はますます輝きを増す。私を番だという彼の目には、私のことがどんなふうに映っているのだろう。蜂蜜色の瞳は、私の言葉を待ちながらキラリと光った。
「私、ルーカスのことが大好きよ。そうね、やっぱり〝番〟っていう感覚はわからないけれど……でも、異性を好きになる気持ちならわかるわ。他の誰かに、あなたのことを渡したくないって思うぐらい、ルーカスのことが好きよ」
「ライラ!!」
正面からぎゅっと抱きしめてくるルーカスを制することは、もうしなかった。その大きな背に自分の腕を回したのは、初めてだったかもしれない。
ルーカスの温もりに安心して、そっと目を閉じた。
なあ、ライラ。同じじゃないか?相手が人間であろうと獣人であろうと、愛しい相手に尽くし合う。そういうことだろ?」
愛しい相手に尽くし合う……
ルーカスを苦しめないために、自分にできることを探す。今の私は、まさしく彼の言う通りなのかもしれない。そして、ルーカスが私にしてくれる全ての行動も、言葉も、また同じこと。
「そうね。その通りだわ」
ルーカスの話が、ストンと胸に落ちた。
「ルーカス」
その名を呼べば、私を見つめ続けていた瞳はますます輝きを増す。私を番だという彼の目には、私のことがどんなふうに映っているのだろう。蜂蜜色の瞳は、私の言葉を待ちながらキラリと光った。
「私、ルーカスのことが大好きよ。そうね、やっぱり〝番〟っていう感覚はわからないけれど……でも、異性を好きになる気持ちならわかるわ。他の誰かに、あなたのことを渡したくないって思うぐらい、ルーカスのことが好きよ」
「ライラ!!」
正面からぎゅっと抱きしめてくるルーカスを制することは、もうしなかった。その大きな背に自分の腕を回したのは、初めてだったかもしれない。
ルーカスの温もりに安心して、そっと目を閉じた。