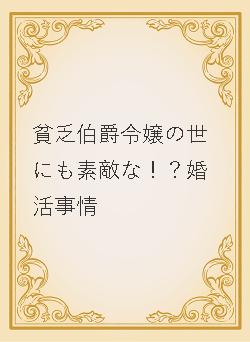「すごく、嫌だと思ったの。ルーカスの横にいるのは、自分がいいって」
「ライラ!!」
すぐにでも抱きついてきそうなルーカスを、手で制す。不満げな彼の顔を見ながら、どうしても聞いて欲しい自分の本心を明かす。
「私は……うん。もう認めるわ。ルーカスのことが、異性として好きだわ。けれど、私の好きは、ルーカスの言う番に向ける想いと同じかと聞かれたら、自信がない」
「ライラ……」
口を挟もうとするルーカスを、再び制す。
「私は人間だから、獣人であるルーカスを、本当の意味では理解できてないと思う。もし私が、あなたと同じ獣人だったら……」
これほど悩まずに、答えを見つけられていただろうか?彼の苦しみを、本当の意味で理解できただろうか?
「ライラ」
愛しさの滲むルーカスの甘い声に、俯きかけていた顔を上げた。そこには思った通り、声音のままのとろけるような笑みを浮かべたルーカスがいた。
「人間に番を理解しろと言っても、無理なものは無理だ。けれど、同族同士だって、同じじゃないか?」
「同じ……?」
首を傾げて彼の言葉を待った。
「たとえば人間同士だって、同じ時間を過ごして、言葉を重ねてきたって、相手のことを本当に全て理解するわけじゃない」
それは……誰だって、いつでも本心を全て晒すわけじゃないけど……
「だからこそ、さらに言葉を重ねて、態度でも示して、少しでも一緒に過ごそうとするだろ?」
確かにそうかもしれないと、コクリと首を縦に振った。ルーカスも満足そうに、頷き返してくる。
「ライラ!!」
すぐにでも抱きついてきそうなルーカスを、手で制す。不満げな彼の顔を見ながら、どうしても聞いて欲しい自分の本心を明かす。
「私は……うん。もう認めるわ。ルーカスのことが、異性として好きだわ。けれど、私の好きは、ルーカスの言う番に向ける想いと同じかと聞かれたら、自信がない」
「ライラ……」
口を挟もうとするルーカスを、再び制す。
「私は人間だから、獣人であるルーカスを、本当の意味では理解できてないと思う。もし私が、あなたと同じ獣人だったら……」
これほど悩まずに、答えを見つけられていただろうか?彼の苦しみを、本当の意味で理解できただろうか?
「ライラ」
愛しさの滲むルーカスの甘い声に、俯きかけていた顔を上げた。そこには思った通り、声音のままのとろけるような笑みを浮かべたルーカスがいた。
「人間に番を理解しろと言っても、無理なものは無理だ。けれど、同族同士だって、同じじゃないか?」
「同じ……?」
首を傾げて彼の言葉を待った。
「たとえば人間同士だって、同じ時間を過ごして、言葉を重ねてきたって、相手のことを本当に全て理解するわけじゃない」
それは……誰だって、いつでも本心を全て晒すわけじゃないけど……
「だからこそ、さらに言葉を重ねて、態度でも示して、少しでも一緒に過ごそうとするだろ?」
確かにそうかもしれないと、コクリと首を縦に振った。ルーカスも満足そうに、頷き返してくる。