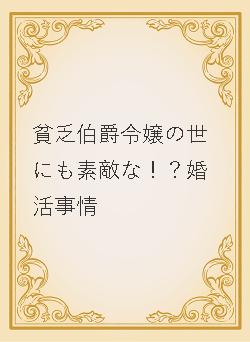「ほおう。ついにか」
グリージア城へ向かう場所の中、ドリーと向かい合わせで座る私。その横に座るルーカス。ルーカスは、人前であろうがなかろうが関係なく、ひたすら私に甘い。纏わりつく。距離なし……彼には遠慮はもちろん、羞恥心とか羞恥心とか、羞恥心なんてものはない。
正面からニヤつきながら見てくるドリーに関係なく、髪に触れ手を握ってくるルーカス。
「カエルは卒業したようだな」
「やっぱり、ライラは俺の番だ。ライラが俺を救ってくれた」
〝救ってくれた〟なんて言い方をされると、なんだかむず痒くなってしまう。でも、ここははっきりさせておかないと。
「番になるかどうかは、未定ですから」
そうやってバシッと言ったのに、2人ともスルーしないで欲しい。なんだか最近、外堀を埋められつつあるんじゃないかと、少しだけ怖くなってくる。どうか、私の気のせいでありますように。
「そうだ!!ルーカスはもうオオカミになれるんでしょ?」
「ああ、もちろん。ライラのおかげでな」
そこでチュッと、こめかみに口付けられてしまう。そのいたたまれなさといったらない。なんの罰ゲームかと……
「そ、それなら、獣化して向かった方が……」
「まあ、速いだろうな。けど、シュトラスが追いつくまでにまだ時間はあるし、体力は温存しておきたいしな」
一理ある。納得。だがしかし、今現在、こうしてドリーの前で手を撫でられ、肩を抱かれ、気まぐれに髪に口付けられ、マーキングとばかりに頭を擦り付けられ……私の中のなにかが、確実に削られていっている。
払っても、払っても、こうして擦り寄ってくるから、無理矢理にでも引き離すことはとうの昔に諦めた。
グリージア城へ向かう場所の中、ドリーと向かい合わせで座る私。その横に座るルーカス。ルーカスは、人前であろうがなかろうが関係なく、ひたすら私に甘い。纏わりつく。距離なし……彼には遠慮はもちろん、羞恥心とか羞恥心とか、羞恥心なんてものはない。
正面からニヤつきながら見てくるドリーに関係なく、髪に触れ手を握ってくるルーカス。
「カエルは卒業したようだな」
「やっぱり、ライラは俺の番だ。ライラが俺を救ってくれた」
〝救ってくれた〟なんて言い方をされると、なんだかむず痒くなってしまう。でも、ここははっきりさせておかないと。
「番になるかどうかは、未定ですから」
そうやってバシッと言ったのに、2人ともスルーしないで欲しい。なんだか最近、外堀を埋められつつあるんじゃないかと、少しだけ怖くなってくる。どうか、私の気のせいでありますように。
「そうだ!!ルーカスはもうオオカミになれるんでしょ?」
「ああ、もちろん。ライラのおかげでな」
そこでチュッと、こめかみに口付けられてしまう。そのいたたまれなさといったらない。なんの罰ゲームかと……
「そ、それなら、獣化して向かった方が……」
「まあ、速いだろうな。けど、シュトラスが追いつくまでにまだ時間はあるし、体力は温存しておきたいしな」
一理ある。納得。だがしかし、今現在、こうしてドリーの前で手を撫でられ、肩を抱かれ、気まぐれに髪に口付けられ、マーキングとばかりに頭を擦り付けられ……私の中のなにかが、確実に削られていっている。
払っても、払っても、こうして擦り寄ってくるから、無理矢理にでも引き離すことはとうの昔に諦めた。