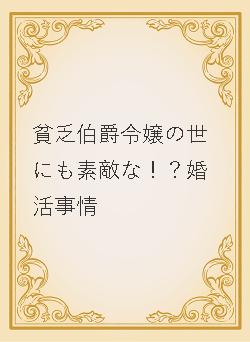「サーヤ」
優しい声音に、心が震える。
「俺が唯一心を許せるのは、サーヤだけだ」
驚いて見上げれば、熱のこもったエメラルドの瞳に囚われてしまう。その瞳に魅せられて、視線を逸らすことができなくなってしまう。
「俺がこの腕の中に抱いていたいのは、サーヤだけだ」
「私、だけ?」
「俺が自分の妻にと望むのは、さや香、サーヤだけだ」
〝サーヤだけ〟と繰り返すエディに、全てを諦めかけていた心が満たされていく。
「エディ……」
喜びつつも戸惑う私を、まるでもう逃がさないとでもいうように、きつくきつく抱きしめてくる。
「どうして……どうして私なの?」
「はじてここでサーヤに出会った時、ああ、俺の相手はこの子だってわかっていた」
最初から?
初対面のあの時、そんな素振りは一切なかったのに……
「ただ、どう見てもソフィアそのものの外見だから、どういうことかと戸惑っていた。見た目はソフィアなのに、匂いが違う。
はじめから、あの王女様は俺の唯一じゃないとわかっていたから、嫁いで来られてどうやり過ごすか、ずっと頭を悩ませていたんだ。もしかして、匂いになにか細工をしたのかとすら考えた。
ああ、この狼の性質は、もちろんエリオットも知ってることだぞ」
優しい声音に、心が震える。
「俺が唯一心を許せるのは、サーヤだけだ」
驚いて見上げれば、熱のこもったエメラルドの瞳に囚われてしまう。その瞳に魅せられて、視線を逸らすことができなくなってしまう。
「俺がこの腕の中に抱いていたいのは、サーヤだけだ」
「私、だけ?」
「俺が自分の妻にと望むのは、さや香、サーヤだけだ」
〝サーヤだけ〟と繰り返すエディに、全てを諦めかけていた心が満たされていく。
「エディ……」
喜びつつも戸惑う私を、まるでもう逃がさないとでもいうように、きつくきつく抱きしめてくる。
「どうして……どうして私なの?」
「はじてここでサーヤに出会った時、ああ、俺の相手はこの子だってわかっていた」
最初から?
初対面のあの時、そんな素振りは一切なかったのに……
「ただ、どう見てもソフィアそのものの外見だから、どういうことかと戸惑っていた。見た目はソフィアなのに、匂いが違う。
はじめから、あの王女様は俺の唯一じゃないとわかっていたから、嫁いで来られてどうやり過ごすか、ずっと頭を悩ませていたんだ。もしかして、匂いになにか細工をしたのかとすら考えた。
ああ、この狼の性質は、もちろんエリオットも知ってることだぞ」