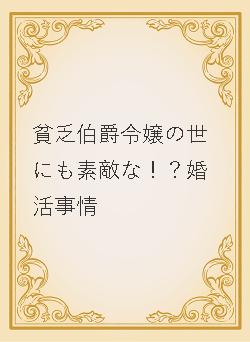「狼流の、誓い、ですか……?」
そう呟いたクラリッサに、エディは変わらず厳しい目を向け続けている。
「狼の愛情表現。それは相手の首元に噛み跡を付けること。俺は今日、多くの観衆の前で、確かにその誓いを立てた」
ハッとして、思わず首筋に手を当てた私を、再びエディの優しい視線が捉えてくる。
「確かに、エドワードはそうしていたな。」
苦笑混じりにエリオットが言う。
だからだ。だから、あの誓いの場で、エディが私の首に噛み付いたタイミングで、拍手が上がったのだ。きっと、狼の血を引く人の性質を知っていたのだろう。もしくは、エディのお母様の国の人かもしれない。
「陛下だけではなく、あの場にいた全ての人間が、その様子を見ていたはずだ。このニセモノの王女には、その噛み跡があるか?」
そんなもの付いているはずがないことは、クラリッサ達も知っている。
「ポリー、確認してくれ」
さすがに異性には確認させられなかったようで、エディは侍女を呼んだ。
「失礼します」
ソフィア王女をその場に座らせたポリーは、その首筋を確認していく。念のため、左も右も。
そう呟いたクラリッサに、エディは変わらず厳しい目を向け続けている。
「狼の愛情表現。それは相手の首元に噛み跡を付けること。俺は今日、多くの観衆の前で、確かにその誓いを立てた」
ハッとして、思わず首筋に手を当てた私を、再びエディの優しい視線が捉えてくる。
「確かに、エドワードはそうしていたな。」
苦笑混じりにエリオットが言う。
だからだ。だから、あの誓いの場で、エディが私の首に噛み付いたタイミングで、拍手が上がったのだ。きっと、狼の血を引く人の性質を知っていたのだろう。もしくは、エディのお母様の国の人かもしれない。
「陛下だけではなく、あの場にいた全ての人間が、その様子を見ていたはずだ。このニセモノの王女には、その噛み跡があるか?」
そんなもの付いているはずがないことは、クラリッサ達も知っている。
「ポリー、確認してくれ」
さすがに異性には確認させられなかったようで、エディは侍女を呼んだ。
「失礼します」
ソフィア王女をその場に座らせたポリーは、その首筋を確認していく。念のため、左も右も。