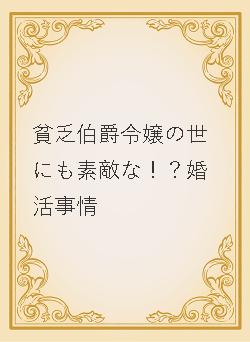先日も訪れた中庭の芝生の一角に、食事の用意をすると、ダーラは下がっていった。今日はパンとスープのみという、簡単なもの。あまり食欲がないことが伝わっているのだろう。スープが具沢山なあたりは、私の体調を気遣ってのことかもしれない。
ニセモノの王女だというのに、気を遣わせてしまうのは申し訳ない。
シートに座ってパンを片手に持ったものの、なかなか食べる気がしない。
「今日は来てくれるかしら?」
食べる代わりに、小声で歌を口ずさんだ。目を閉じていると、すぐになにかの気配を感じはじめる。小走りに来るものもいれば、そろりそろりと近付いてくるものもいるようだ。
足に手をかけられたのを合図に、そっと目を開けた。
「今日も来てくれたのね」
足によじ登ってきたのは、私が助けた猫だった。他にも、数種類の鳥やうさぎもいる。それぞれつぶらな瞳を、一心に私に向けている。
『元気ないね』
そう声をかけた猫は、まるで私を心配するような視線を向けてくる。
「そうかも……うん。いろいろとね、悩んじゃって」
『ふうん』
一応、探るような仕草を見せてくれるものの、そこは気まぐれな猫のこと。それ以上、慰めの言葉も励ましの言葉もくれない。
私も、来てくれただけでいいかと納得して、鼻歌を歌った。
ニセモノの王女だというのに、気を遣わせてしまうのは申し訳ない。
シートに座ってパンを片手に持ったものの、なかなか食べる気がしない。
「今日は来てくれるかしら?」
食べる代わりに、小声で歌を口ずさんだ。目を閉じていると、すぐになにかの気配を感じはじめる。小走りに来るものもいれば、そろりそろりと近付いてくるものもいるようだ。
足に手をかけられたのを合図に、そっと目を開けた。
「今日も来てくれたのね」
足によじ登ってきたのは、私が助けた猫だった。他にも、数種類の鳥やうさぎもいる。それぞれつぶらな瞳を、一心に私に向けている。
『元気ないね』
そう声をかけた猫は、まるで私を心配するような視線を向けてくる。
「そうかも……うん。いろいろとね、悩んじゃって」
『ふうん』
一応、探るような仕草を見せてくれるものの、そこは気まぐれな猫のこと。それ以上、慰めの言葉も励ましの言葉もくれない。
私も、来てくれただけでいいかと納得して、鼻歌を歌った。