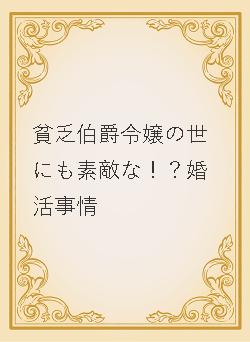「なに、これ……」
麗かな春の昼下がり。
何気なく見つめたていた水晶が映し出したのは、数年経ったであろう自分の姿だった。
綺麗に着飾った私の手を取るのは、この国の王太子、アルフレッド・グリージアだった。
私を見つめる彼の瞳はどこまでも甘く、彼を見つめ返す私の瞳もまた同じだった。
そのまま水晶を見つめていると、映し出される映像から、どうやら私は殿下の婚約者であろうことに気が付いた。
しかも、この様子からすると、お互いに想い合って。
アルフレッドのお相手ということは、将来のグリージア王国の王妃、つまり国母になるということだ。
そんな大役が、私に務まるとは思えない。嬉しさよりも恐怖心の方が大きかった。
けれど、水晶が見せる未来の私は、幸せそのものの顔をしている。アルフレッドがそれほどまでに私のことを想い、大切にしてくれているのだろう。
避けられない未来ならば、殿下を信じてその流れに身を任せるしかないと、未来のその様子を受け入れた。
麗かな春の昼下がり。
何気なく見つめたていた水晶が映し出したのは、数年経ったであろう自分の姿だった。
綺麗に着飾った私の手を取るのは、この国の王太子、アルフレッド・グリージアだった。
私を見つめる彼の瞳はどこまでも甘く、彼を見つめ返す私の瞳もまた同じだった。
そのまま水晶を見つめていると、映し出される映像から、どうやら私は殿下の婚約者であろうことに気が付いた。
しかも、この様子からすると、お互いに想い合って。
アルフレッドのお相手ということは、将来のグリージア王国の王妃、つまり国母になるということだ。
そんな大役が、私に務まるとは思えない。嬉しさよりも恐怖心の方が大きかった。
けれど、水晶が見せる未来の私は、幸せそのものの顔をしている。アルフレッドがそれほどまでに私のことを想い、大切にしてくれているのだろう。
避けられない未来ならば、殿下を信じてその流れに身を任せるしかないと、未来のその様子を受け入れた。