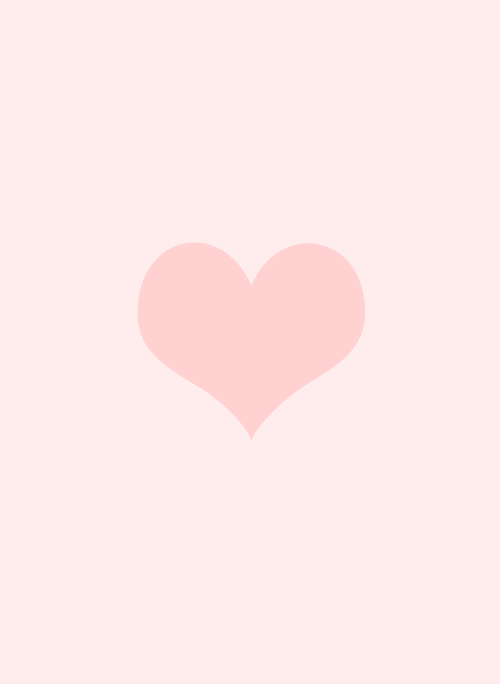「おっと、そうだそうだ。俺の話なんかどうだっていいんだよ。下手な理由つけて誘っても応じてはくれないだろうなって適当言ってたつもりが、どうにも作品の話題とあっちゃあ熱が入っちまう。こりゃ反省だ」
「え? 違うの?」
「おう。珍しくも誘った上、珍しくも尋ねてやるがよ。流石にちょっと変じゃねえか? お前、じいちゃんが亡くなった時も、そこまで凹んでなかったろ? ……って言い方もどうかとは思うがよ、ほんとそれ以外の言い方が思い浮かばんくらい、何か考え込んでるように見えるんだよ。大丈夫か?」
それは、とても意外な言い分だった。
ラノベの感想が聞きたいから、と誘われた時は決まって、勝手気ままに話すだけ話して、僕がそれに適当に答えて、なるほどそうか、それも有りだなって勝手に納得して、はいさようなら。その結果として、あくまで結果として、僕が勝手に気が紛れているという状況だった。
ユウが直接何かを尋ねて来ることなど、今まで一度たりとも無かった。
「——面倒だな」
語るのも、その相手がこいつなのも。
「そう言うなって。まぁ、言いたくないならそれで良いんだけどよ。抱えられなくなる内に吐き出した方が良いことだってあるぞ。って、一応忠告とかしておくさ」
慰めるように、諭すように、ユウはそれだけ言って、食事を再開した。
ガツガツと、柄にもなく横暴な食いっぷりで。
分かってる。分かってるさ。
「…………その内、な」
口にしてから、祖父と同じようなことを言っていることに気が付いた。
「え? 違うの?」
「おう。珍しくも誘った上、珍しくも尋ねてやるがよ。流石にちょっと変じゃねえか? お前、じいちゃんが亡くなった時も、そこまで凹んでなかったろ? ……って言い方もどうかとは思うがよ、ほんとそれ以外の言い方が思い浮かばんくらい、何か考え込んでるように見えるんだよ。大丈夫か?」
それは、とても意外な言い分だった。
ラノベの感想が聞きたいから、と誘われた時は決まって、勝手気ままに話すだけ話して、僕がそれに適当に答えて、なるほどそうか、それも有りだなって勝手に納得して、はいさようなら。その結果として、あくまで結果として、僕が勝手に気が紛れているという状況だった。
ユウが直接何かを尋ねて来ることなど、今まで一度たりとも無かった。
「——面倒だな」
語るのも、その相手がこいつなのも。
「そう言うなって。まぁ、言いたくないならそれで良いんだけどよ。抱えられなくなる内に吐き出した方が良いことだってあるぞ。って、一応忠告とかしておくさ」
慰めるように、諭すように、ユウはそれだけ言って、食事を再開した。
ガツガツと、柄にもなく横暴な食いっぷりで。
分かってる。分かってるさ。
「…………その内、な」
口にしてから、祖父と同じようなことを言っていることに気が付いた。