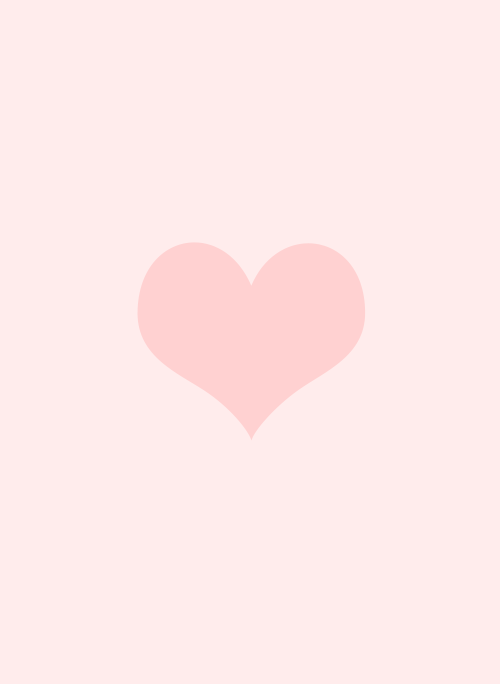「おばあちゃん、これって?」
唯一知っているであろう祖母に尋ねる。
しかし答えは、
「えっと——ええ、あの人が創ったもので間違いないわ。けれど——私は、なんだけど、そのタイトルには見覚えないわね。そう多くの曲を創った訳でもないから、見ていれば、聞いていれば、忘れていても思い出せる筈だもの」
そんなことを言った。
疑うことなく、僕はその言葉をそのまま受け入れる。
そっか、と軽く返事が出来るのも、御年八十になる祖母の記憶力たるや相当なもので、加えて認知症の『に』の字もないくらい、しっかりとしているからだ。
しかし。
今でこそあまり驚きもしなくなったが、じいちゃんが作曲をしていたという話も、当人が亡くなった後で知ったことだ。
きっかけは何気ないことだった。
祖母の部屋で見つけたオルゴールの音色が、有名でもなければ聴いたこともない曲で、且つ題の入っていない箱だったものだから、気になって尋ねてみたのだ。
教えてくれるか否かは半々だったけれど、祖母は意外にも渋ることなく、寧ろ誇らしげに語って聞かせてくれた。
あの人が創った、特別で特別で仕方のないものなのよ、と。
「りえん……らいえん…? 読み方も分かんないね」
「どれどれ?」
言いながら、ずいと横方覗き込んでくる母。
しかしながら間髪入れず「うん、分からない」と言い放つ。少しくらい頑張ってよ。
「ピアノの楽譜ってこと意外、私には分かんないわ。音色も思い浮かばないなー。ねぇ拓海、ちょっと弾けない?」
母は、何とも無しに、とても意外なことを口にした。
僕だけじゃなく、母だってそんなこと、口にするのは避けていた筈なのに。
何を思ったのだろう。
母からすれば肉親である祖父の死と、関係が無いとは考えにくいけれど。
そんなこと思いながら、そう言えばと思い返す。
母からも、祖父の話は聞いたことがない。
僕が祖父にものを尋ねる時、割と母も同じ場所に居合わせることは多かった気がするのだが。
肉親も肉親、それこそ、祖父の仕事や活動について、知らない筈はない。
そんな母も、祖母も知らない名前、音色、か。
「——やだよ。僕は“弾けない”から」
その一言だけが、今の僕を象徴する言葉だ。
チラと窺った母は、
「ま、それもそうね。別に良いけど。特に執着があるって訳でもないし」
あっけらかんと、そのままさっさと楽譜から視線を外してしまった。
「何だよ、それ。じゃあ聞かないでよね」
「べっつに、ものは試しってやつよ、忘れなさい」
きっぱりさらりと言い捨てて、母は再び作業に戻る。
いつの間にか会話からも外れていた祖母は、既に部屋の中にはいない。
「…………はぁ、まったく」
独り言ちて肩を落とす、真夏の昼下がり。
唯一知っているであろう祖母に尋ねる。
しかし答えは、
「えっと——ええ、あの人が創ったもので間違いないわ。けれど——私は、なんだけど、そのタイトルには見覚えないわね。そう多くの曲を創った訳でもないから、見ていれば、聞いていれば、忘れていても思い出せる筈だもの」
そんなことを言った。
疑うことなく、僕はその言葉をそのまま受け入れる。
そっか、と軽く返事が出来るのも、御年八十になる祖母の記憶力たるや相当なもので、加えて認知症の『に』の字もないくらい、しっかりとしているからだ。
しかし。
今でこそあまり驚きもしなくなったが、じいちゃんが作曲をしていたという話も、当人が亡くなった後で知ったことだ。
きっかけは何気ないことだった。
祖母の部屋で見つけたオルゴールの音色が、有名でもなければ聴いたこともない曲で、且つ題の入っていない箱だったものだから、気になって尋ねてみたのだ。
教えてくれるか否かは半々だったけれど、祖母は意外にも渋ることなく、寧ろ誇らしげに語って聞かせてくれた。
あの人が創った、特別で特別で仕方のないものなのよ、と。
「りえん……らいえん…? 読み方も分かんないね」
「どれどれ?」
言いながら、ずいと横方覗き込んでくる母。
しかしながら間髪入れず「うん、分からない」と言い放つ。少しくらい頑張ってよ。
「ピアノの楽譜ってこと意外、私には分かんないわ。音色も思い浮かばないなー。ねぇ拓海、ちょっと弾けない?」
母は、何とも無しに、とても意外なことを口にした。
僕だけじゃなく、母だってそんなこと、口にするのは避けていた筈なのに。
何を思ったのだろう。
母からすれば肉親である祖父の死と、関係が無いとは考えにくいけれど。
そんなこと思いながら、そう言えばと思い返す。
母からも、祖父の話は聞いたことがない。
僕が祖父にものを尋ねる時、割と母も同じ場所に居合わせることは多かった気がするのだが。
肉親も肉親、それこそ、祖父の仕事や活動について、知らない筈はない。
そんな母も、祖母も知らない名前、音色、か。
「——やだよ。僕は“弾けない”から」
その一言だけが、今の僕を象徴する言葉だ。
チラと窺った母は、
「ま、それもそうね。別に良いけど。特に執着があるって訳でもないし」
あっけらかんと、そのままさっさと楽譜から視線を外してしまった。
「何だよ、それ。じゃあ聞かないでよね」
「べっつに、ものは試しってやつよ、忘れなさい」
きっぱりさらりと言い捨てて、母は再び作業に戻る。
いつの間にか会話からも外れていた祖母は、既に部屋の中にはいない。
「…………はぁ、まったく」
独り言ちて肩を落とす、真夏の昼下がり。