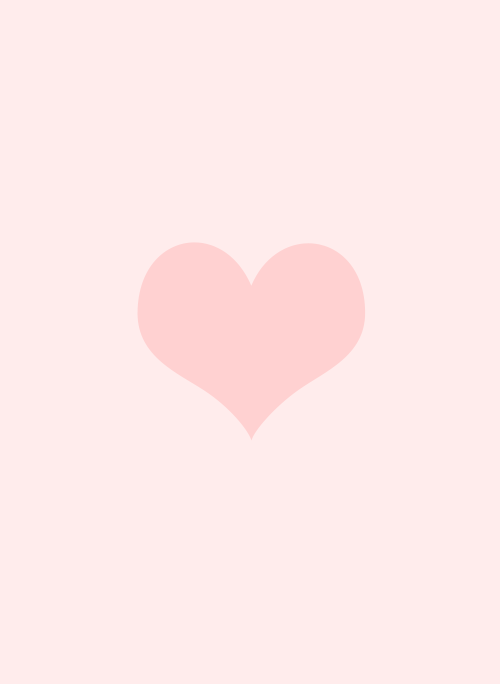布団を頭までかぶって、深い溜息を吐く。
『好きなのか?』
(ぶっ――! な、何よ急に…!)
虚を突かれた質問に思わず唾を誤嚥して咽る汐里。それは離れたデスクで作業を続ける高橋先生にも聞こえてしまっていたようで「何かあった?」と心配される始末だ。
何とか誤魔化してここへの侵入を防ぐと、とんでもない無礼を働いた琢磨を精神的に睨む。
『いやほら、ここってさっきの生徒会長? が使ってたところだろ。におい嗅いで興奮してるのかと思って』
(な…! どんだけデリカシーないのよこの居候。溜息よ、溜息)
『えらく深いな。それに、さっき一瞬「輝くん」って』
変な所で無駄に鋭い琢磨に呆れて、汐里はまた一つ大きな溜息が漏れた。
(学校では出さないようにしてるんだけどね。私と会ちょ――輝くんは、幼稚園からの幼馴染なのよ、ただのね)
『強調すると信憑性上がるぞ』
(五月蠅い。えっと、それで、ここ最近ずっと姿も見なかったものだから、どうしてるのかなったちょっと心配になってたの。ほんと、それだけ)
『ふぅん。それで、好きなのか?』
お前は人の話を聞いていなかったのか?
思わずそう突っ込みたくなった衝動を抑えて、あくまで理知的な返しを試みようとする汐里に、しかし琢磨はまた違った観点から指摘した。
『人間、自分のことには無頓着なもんでな。さっきまでは七十前後だった君の脈だけどな、あいつに会った瞬間、馬鹿みたいに跳ね上がったぞ。あ、今測っても無駄だぞ、落ち着いたし』
(な……! 何でそんなこと分かるのよ!)
『生前は看護学生だったからってのが理由に入るのかは分からんが、そういうのには敏感なんだよ。相手の基準値を知っておくのが癖みたいなもんなんだよ』
なんて質の悪い。苦手意識を持つのはお互い様だった。
琢磨の指摘通り、その瞬間の汐里に脈は確かに上昇していた。それは不思議なもので、汐里自身も少なからず感じてはいたことだった。
しかしそれを否定し琢磨に噛みついたのは、それが汐里にとっては有り得ない感情だったからだ。いや、正しくはそれも合ってはいるのだが、上昇の理由は恋などという感情の元ではなかった。
昔から自分とは違って何でも出来る輝典が羨ましくて、同時に何もない自分と比較すると妬ましくて、しかし同時にいつでも優しいその背中に憧れていて。
言ってみれば、汐里の中にあるのは、尊敬や羨望といった思いだ。
好きだから緊張するのではなく、目標がすぐ傍にあるから。
しかし、そんなこと、どうせ馬鹿にするだろうからと琢磨には言わなかった。
『休み時間まであと何分だ?』
ふと、琢磨が尋ねた。
ちらと見た腕時計の針は、もう三限目を終える時間を指そうとしていた。授業の途中で抜け出してきたから既に時間が迫っていたのは当然なのだが、存外と時間の経過を速く感じて、汐里はやっぱりちょっと勿体なかったかなとも思った。
(もうちょっとで終わるかな)
『そうか』
ぶっきらぼうに返してそれ以上何も言わない琢磨に、聊か疑問を抱く汐里。
しかし、それが何だと分析し始めるより早く、授業終了を知らせるチャイムが鳴り響いた。
「終わったわね。陸上さん、大丈夫?」
そんな声とともに、開かれたカーテンから高橋先生が入って来た。のそのそと亀のように布団から頭を出した汐里に笑いながら、顔色を見ると安心して微笑んだ。
「大丈夫そうね。自分で歩け――っと、来たみたいね」
話し途中で不意に聞こえたノックの音。次いで開け放たれた扉から、美希がパタパタと駆けて来た。
「こんにちは高橋先生」
心配そうな表情で友人しか目に入っていないかと思えば、礼儀を欠かず丁寧に挨拶。
それに短く「はいこんにちは」と返されると、ようやく汐里の方へ視線を向けた。
「調子、どう?」
未だ布団にくるまっていた汐里を見て、美希は益々不安の色を濃くした。
先の別れ際のテンションを忘れたのだろうか。
「うーん、ちょっとまだ……」
『は、ちょ、おい待てこら…! そんなこと言ったら――』
憤慨する琢磨の予想は的中。美希の顔色が、一瞬にして悪くなった。
「まだどこか悪いの…? 迎え呼ぶ? 救急車呼ぶ?」
おろおろ、わなわなと震えながらスマホを取り出してそんなことを言った。
そこで助け舟を渡したのは、傍から二人のやり取りを眺めていた高橋先生。美希からスマホを取り上げ、
「没収。まだ放課前でしょ?」
「で、でも、しおが…!」
どんどんと悪くなっていく顔色。
流れと嘘で休んでいた汐里より、よっぽど病人らしかった。
自分を心配してくれた友人を一通り弄って満足すると、ようやくとネタ晴らし。堪えきれない笑いを漏らしながら、汐里は布団から出た。
「ごめん、美希。嘘」
「嘘って――え…?」
「もう何ともないよ、元気。心配かけてごめんね」
「心配ないって……」
美希の身体から一気に抜けていく力。
ぺたんと地面にへたり込み、俯いてしまった。
そのまましばらく何も言わず動きもしないので、流石にやり過ぎたかと反省しながら肩に手をやると顔を上げ、汐里の目を真っ直ぐに見つめた。
その顔には、目元から流れる一粒の涙と共に、怒りの色が見て取れた。
やばい、と思った刹那、
「も、もう…! 冗談なしに心配してたのに、しおは…! せっかく帰りに寄って奢ろうと思ってたクレープ、私と知音だけで食べちゃうんだから!」
怒られた。と言うか、叱られた。説教された。
無意識下でサディスト気質の汐里は、たまにこうして冗談を言っては真面目で素直な美希を困らせ、挙句自爆するというのがお決まりの結末だった。その度に美希は「しばらく反省しなさい!」と二日は口を聞いてくれないことも。
「山田さん」
ふと響くのは、低く重く伝わる高橋先生の声。
「は、はい…?」
「こっちも忘れて貰っちゃ困るのよね」
そう言ってひらひらと手の上で弄ぶのは、たった今美希から取り上げたスマホだ。
「電源オフ、バッグ保管が校則の筈よ?」
「え、えっと……そう、しおに万が一のことがあると思って…!」
「放課後、生徒指導室まで」
「しおが――」
「生徒指導室まで」
「ひゃっ……は、はい…!」
久々に踏み抜いたかと思われた地雷は、またしても傍から冷静に眺めていた高橋先生の一言で不発に終わった。
思わず漏れた深い安堵の息に、しかし心の中では琢磨が突っ込んでいた。
『あーあー。原因を作ったのは確かに俺だったが、これは完全に君が悪かったな』
(えぇ、迂闊だったわ……あんまり反応が良くて可愛いものだから、つい)
『さらっと怖いこと言うなよ。とりあえず、スマホ取られた要因の一端は君にもあるわけだから、放課後着いて行ってやれよな』
(い、言われなくても分かってるわよ…)
後悔先に立たず、とはよく言ったものだった。
『好きなのか?』
(ぶっ――! な、何よ急に…!)
虚を突かれた質問に思わず唾を誤嚥して咽る汐里。それは離れたデスクで作業を続ける高橋先生にも聞こえてしまっていたようで「何かあった?」と心配される始末だ。
何とか誤魔化してここへの侵入を防ぐと、とんでもない無礼を働いた琢磨を精神的に睨む。
『いやほら、ここってさっきの生徒会長? が使ってたところだろ。におい嗅いで興奮してるのかと思って』
(な…! どんだけデリカシーないのよこの居候。溜息よ、溜息)
『えらく深いな。それに、さっき一瞬「輝くん」って』
変な所で無駄に鋭い琢磨に呆れて、汐里はまた一つ大きな溜息が漏れた。
(学校では出さないようにしてるんだけどね。私と会ちょ――輝くんは、幼稚園からの幼馴染なのよ、ただのね)
『強調すると信憑性上がるぞ』
(五月蠅い。えっと、それで、ここ最近ずっと姿も見なかったものだから、どうしてるのかなったちょっと心配になってたの。ほんと、それだけ)
『ふぅん。それで、好きなのか?』
お前は人の話を聞いていなかったのか?
思わずそう突っ込みたくなった衝動を抑えて、あくまで理知的な返しを試みようとする汐里に、しかし琢磨はまた違った観点から指摘した。
『人間、自分のことには無頓着なもんでな。さっきまでは七十前後だった君の脈だけどな、あいつに会った瞬間、馬鹿みたいに跳ね上がったぞ。あ、今測っても無駄だぞ、落ち着いたし』
(な……! 何でそんなこと分かるのよ!)
『生前は看護学生だったからってのが理由に入るのかは分からんが、そういうのには敏感なんだよ。相手の基準値を知っておくのが癖みたいなもんなんだよ』
なんて質の悪い。苦手意識を持つのはお互い様だった。
琢磨の指摘通り、その瞬間の汐里に脈は確かに上昇していた。それは不思議なもので、汐里自身も少なからず感じてはいたことだった。
しかしそれを否定し琢磨に噛みついたのは、それが汐里にとっては有り得ない感情だったからだ。いや、正しくはそれも合ってはいるのだが、上昇の理由は恋などという感情の元ではなかった。
昔から自分とは違って何でも出来る輝典が羨ましくて、同時に何もない自分と比較すると妬ましくて、しかし同時にいつでも優しいその背中に憧れていて。
言ってみれば、汐里の中にあるのは、尊敬や羨望といった思いだ。
好きだから緊張するのではなく、目標がすぐ傍にあるから。
しかし、そんなこと、どうせ馬鹿にするだろうからと琢磨には言わなかった。
『休み時間まであと何分だ?』
ふと、琢磨が尋ねた。
ちらと見た腕時計の針は、もう三限目を終える時間を指そうとしていた。授業の途中で抜け出してきたから既に時間が迫っていたのは当然なのだが、存外と時間の経過を速く感じて、汐里はやっぱりちょっと勿体なかったかなとも思った。
(もうちょっとで終わるかな)
『そうか』
ぶっきらぼうに返してそれ以上何も言わない琢磨に、聊か疑問を抱く汐里。
しかし、それが何だと分析し始めるより早く、授業終了を知らせるチャイムが鳴り響いた。
「終わったわね。陸上さん、大丈夫?」
そんな声とともに、開かれたカーテンから高橋先生が入って来た。のそのそと亀のように布団から頭を出した汐里に笑いながら、顔色を見ると安心して微笑んだ。
「大丈夫そうね。自分で歩け――っと、来たみたいね」
話し途中で不意に聞こえたノックの音。次いで開け放たれた扉から、美希がパタパタと駆けて来た。
「こんにちは高橋先生」
心配そうな表情で友人しか目に入っていないかと思えば、礼儀を欠かず丁寧に挨拶。
それに短く「はいこんにちは」と返されると、ようやく汐里の方へ視線を向けた。
「調子、どう?」
未だ布団にくるまっていた汐里を見て、美希は益々不安の色を濃くした。
先の別れ際のテンションを忘れたのだろうか。
「うーん、ちょっとまだ……」
『は、ちょ、おい待てこら…! そんなこと言ったら――』
憤慨する琢磨の予想は的中。美希の顔色が、一瞬にして悪くなった。
「まだどこか悪いの…? 迎え呼ぶ? 救急車呼ぶ?」
おろおろ、わなわなと震えながらスマホを取り出してそんなことを言った。
そこで助け舟を渡したのは、傍から二人のやり取りを眺めていた高橋先生。美希からスマホを取り上げ、
「没収。まだ放課前でしょ?」
「で、でも、しおが…!」
どんどんと悪くなっていく顔色。
流れと嘘で休んでいた汐里より、よっぽど病人らしかった。
自分を心配してくれた友人を一通り弄って満足すると、ようやくとネタ晴らし。堪えきれない笑いを漏らしながら、汐里は布団から出た。
「ごめん、美希。嘘」
「嘘って――え…?」
「もう何ともないよ、元気。心配かけてごめんね」
「心配ないって……」
美希の身体から一気に抜けていく力。
ぺたんと地面にへたり込み、俯いてしまった。
そのまましばらく何も言わず動きもしないので、流石にやり過ぎたかと反省しながら肩に手をやると顔を上げ、汐里の目を真っ直ぐに見つめた。
その顔には、目元から流れる一粒の涙と共に、怒りの色が見て取れた。
やばい、と思った刹那、
「も、もう…! 冗談なしに心配してたのに、しおは…! せっかく帰りに寄って奢ろうと思ってたクレープ、私と知音だけで食べちゃうんだから!」
怒られた。と言うか、叱られた。説教された。
無意識下でサディスト気質の汐里は、たまにこうして冗談を言っては真面目で素直な美希を困らせ、挙句自爆するというのがお決まりの結末だった。その度に美希は「しばらく反省しなさい!」と二日は口を聞いてくれないことも。
「山田さん」
ふと響くのは、低く重く伝わる高橋先生の声。
「は、はい…?」
「こっちも忘れて貰っちゃ困るのよね」
そう言ってひらひらと手の上で弄ぶのは、たった今美希から取り上げたスマホだ。
「電源オフ、バッグ保管が校則の筈よ?」
「え、えっと……そう、しおに万が一のことがあると思って…!」
「放課後、生徒指導室まで」
「しおが――」
「生徒指導室まで」
「ひゃっ……は、はい…!」
久々に踏み抜いたかと思われた地雷は、またしても傍から冷静に眺めていた高橋先生の一言で不発に終わった。
思わず漏れた深い安堵の息に、しかし心の中では琢磨が突っ込んでいた。
『あーあー。原因を作ったのは確かに俺だったが、これは完全に君が悪かったな』
(えぇ、迂闊だったわ……あんまり反応が良くて可愛いものだから、つい)
『さらっと怖いこと言うなよ。とりあえず、スマホ取られた要因の一端は君にもあるわけだから、放課後着いて行ってやれよな』
(い、言われなくても分かってるわよ…)
後悔先に立たず、とはよく言ったものだった。