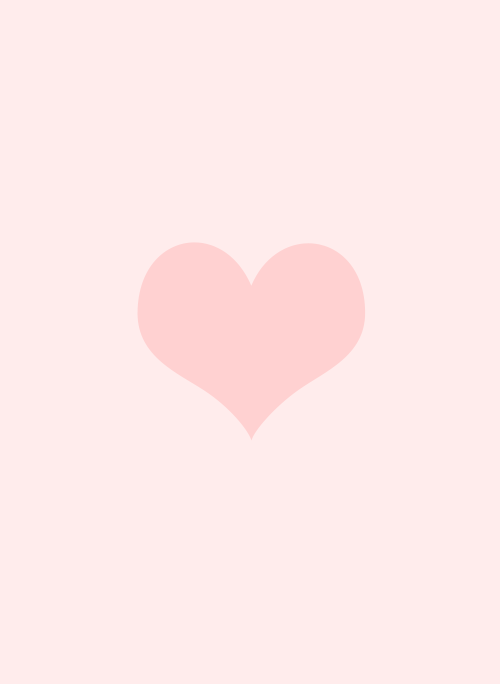泣き止んで暫く。
今更な痴態に悶絶する汐里である。
それも少しして収まると、盛大な溜息が零れた。
「多分、琢磨みたいな人なんだろうなー、なんて」
『脈絡なく人の名前を出さないでもらえるか? 何の話だよ』
「夫にするならってやつ。口やかましい癖に優しくて、お節介で。きっと、一緒に暮らしてて幸せな人って、琢磨みたいな男性なんだと思う」
『よくもまぁ恥ずかし気もなく言えるな、そんなこと。ただお生憎様、俺には実体がないからな。一緒に居てやることは出来ん』
「分かってるよ、そんなこと。あーあ、実体ある人だったら良かったのに」
実体があればどうされていたのか。
ともあれ。
目下、考えるべきは先刻の渦中に起きた出来事だ。
汐里は確かに、ダイヤを吐いていた。
それも、これまでのものとは比べものにならない大きさのものを。
加えて、今までにないものまで混ざっているものを。
ほんの僅かばかりではあるが、赤みがかったそれは血液に他ならない。
つまりはもう、限界が近いということ。
いや。日付が確実である以上、その近さは火を見るよりも明らかだ。
あまりダイヤを吐かないことに胡坐をかいていた。
「ま、なるようにしかならないよ。琢磨の考えることじゃないって」
『心読むな悪魔。それに、勝手に呼び捨てるなよな』
「ダメ? 私は琢磨のこと好きよ?」
『お前な、またそう返しにくいことをこんなタイミングで言うか、普通? はぁ、もう分かったよ、勝手にしてくれ』
「ん、勝手に好きにするね。あぁ、あと勝手ついでに一つだけお願いがあるんだけどさ」
『何だ? 別に俺の身体でもないんだから、許可なんて――』
「妹さん――」
割って入ってそう零した汐里に、琢磨は言葉を失った。
妹さん。
それはつまり、
「琢磨の、心残りだよ」
今更な痴態に悶絶する汐里である。
それも少しして収まると、盛大な溜息が零れた。
「多分、琢磨みたいな人なんだろうなー、なんて」
『脈絡なく人の名前を出さないでもらえるか? 何の話だよ』
「夫にするならってやつ。口やかましい癖に優しくて、お節介で。きっと、一緒に暮らしてて幸せな人って、琢磨みたいな男性なんだと思う」
『よくもまぁ恥ずかし気もなく言えるな、そんなこと。ただお生憎様、俺には実体がないからな。一緒に居てやることは出来ん』
「分かってるよ、そんなこと。あーあ、実体ある人だったら良かったのに」
実体があればどうされていたのか。
ともあれ。
目下、考えるべきは先刻の渦中に起きた出来事だ。
汐里は確かに、ダイヤを吐いていた。
それも、これまでのものとは比べものにならない大きさのものを。
加えて、今までにないものまで混ざっているものを。
ほんの僅かばかりではあるが、赤みがかったそれは血液に他ならない。
つまりはもう、限界が近いということ。
いや。日付が確実である以上、その近さは火を見るよりも明らかだ。
あまりダイヤを吐かないことに胡坐をかいていた。
「ま、なるようにしかならないよ。琢磨の考えることじゃないって」
『心読むな悪魔。それに、勝手に呼び捨てるなよな』
「ダメ? 私は琢磨のこと好きよ?」
『お前な、またそう返しにくいことをこんなタイミングで言うか、普通? はぁ、もう分かったよ、勝手にしてくれ』
「ん、勝手に好きにするね。あぁ、あと勝手ついでに一つだけお願いがあるんだけどさ」
『何だ? 別に俺の身体でもないんだから、許可なんて――』
「妹さん――」
割って入ってそう零した汐里に、琢磨は言葉を失った。
妹さん。
それはつまり、
「琢磨の、心残りだよ」