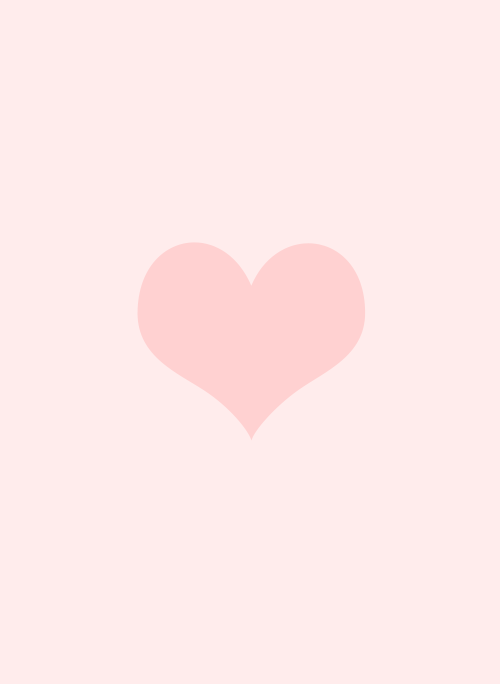「おうえ、ごほっ、う、ぇ…」
ギリギリ家に辿り着けていて良かった。
知音の前でもう一度こんな姿を見せてしまっては、流石に語らない訳にはいかなくなる。
美希の前など尚更だ。
それならせめて、
「汐里…!」
せめて偽母たる渚になら、ちょっとくらい弱音な場面を見せたって罰は当たるまい。
「具合が悪いの…? は、はやく病院に――」
何だ。
琢磨は溜息を吐いた。
汐里はあんな風にして言っていたが、その実とても優しい人じゃないか。
偽物で紛い物なら、ここまでの表情を浮かべられる筈はない。
道端でたまたま見かけた他人に声をかけるのとはわけが違う。
温かい。
「大丈夫、大丈夫だよお母さん……ありがと、すぐに善くなるから」
「そ、そう…? それなら良いんだけど……悪くなったり治まらなかったら、すぐに言ってね」
「うん。ありがと」
そう言って、本当ならリビングかどこかへ退いていくものだと思っていたら、
「まだ病み上がりなんだから。無理は禁物よ」
渚はそう言いながら、傍らからずっと背中を摩り続けている。
ああ、何て温かいのだろう。
微睡みかける意識をしかし寸でのところで縫い留めながら、一旦収まった吐き気のままに、改めて礼を一つ置いてから自室へと戻った。
ふぅと一息吐くと、琢磨はそのままベッドへとダイブした。
捲れたスカートの感覚なんかも気にせずに。
汐里の人格がいれば、『もっと女の子らしくしてよね!』と怒鳴られている頃合いだろう。
何だか無性に懐かしくも感じるやり取りだ。
気配――どこかからまた声を出してくるんだろうな、という感覚もまるでない。
「はぁ…」
一層深い溜息を吐いて、ふと見やった本棚。
ジャンル別、背の低いもの高いものと綺麗に並べられたそれらの中に、薄い、表題の見えない本が目に留まった。
ベッドから起き上がり、本棚へと歩いてそれを手に取る。
「これ――」
表紙も無題。
開いた一ページ目には、日付、天気、そしてその日の出来事らしい何かが羅列してある。
去年の日付。
ある日には、てるくんと少し話すことが出来た。生徒会が忙しそう。
知音と美希が――
ある日には、てるくんがこけたのを見てしまった。つい吹き出しそうになってやめた。
知音がジュースを奢ってくれた――
ある日には、ある日のその頭にはどれも、てるくん――てるくん――そればかりが並んでいた。
そんな中で。
ギリギリ家に辿り着けていて良かった。
知音の前でもう一度こんな姿を見せてしまっては、流石に語らない訳にはいかなくなる。
美希の前など尚更だ。
それならせめて、
「汐里…!」
せめて偽母たる渚になら、ちょっとくらい弱音な場面を見せたって罰は当たるまい。
「具合が悪いの…? は、はやく病院に――」
何だ。
琢磨は溜息を吐いた。
汐里はあんな風にして言っていたが、その実とても優しい人じゃないか。
偽物で紛い物なら、ここまでの表情を浮かべられる筈はない。
道端でたまたま見かけた他人に声をかけるのとはわけが違う。
温かい。
「大丈夫、大丈夫だよお母さん……ありがと、すぐに善くなるから」
「そ、そう…? それなら良いんだけど……悪くなったり治まらなかったら、すぐに言ってね」
「うん。ありがと」
そう言って、本当ならリビングかどこかへ退いていくものだと思っていたら、
「まだ病み上がりなんだから。無理は禁物よ」
渚はそう言いながら、傍らからずっと背中を摩り続けている。
ああ、何て温かいのだろう。
微睡みかける意識をしかし寸でのところで縫い留めながら、一旦収まった吐き気のままに、改めて礼を一つ置いてから自室へと戻った。
ふぅと一息吐くと、琢磨はそのままベッドへとダイブした。
捲れたスカートの感覚なんかも気にせずに。
汐里の人格がいれば、『もっと女の子らしくしてよね!』と怒鳴られている頃合いだろう。
何だか無性に懐かしくも感じるやり取りだ。
気配――どこかからまた声を出してくるんだろうな、という感覚もまるでない。
「はぁ…」
一層深い溜息を吐いて、ふと見やった本棚。
ジャンル別、背の低いもの高いものと綺麗に並べられたそれらの中に、薄い、表題の見えない本が目に留まった。
ベッドから起き上がり、本棚へと歩いてそれを手に取る。
「これ――」
表紙も無題。
開いた一ページ目には、日付、天気、そしてその日の出来事らしい何かが羅列してある。
去年の日付。
ある日には、てるくんと少し話すことが出来た。生徒会が忙しそう。
知音と美希が――
ある日には、てるくんがこけたのを見てしまった。つい吹き出しそうになってやめた。
知音がジュースを奢ってくれた――
ある日には、ある日のその頭にはどれも、てるくん――てるくん――そればかりが並んでいた。
そんな中で。