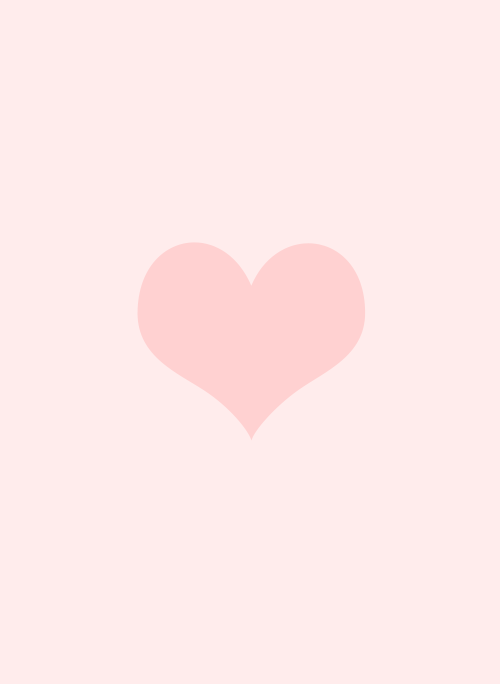「俺になっちまったけど、そのまま帰っていいのか? そういえばな話なんだが、何気にこの数ヶ月の中で初めてな気がするぞ」
立ち止まり、琢磨がそう指摘すると、
『寧ろ都合が良いかな。そのまま帰ってくれる?』
「わ、分かった」
都合が良いとは。その言葉に疑問を抱きながらも、琢磨は既に見慣れた門を通り抜け、扉を開けて家に入った。
靴を脱いで揃えて置いて、リビングの方へ顔を出した。
「ただいまー」
何のことも無くそう言うと、話しかけた相手である母親は、勢いよく振り返って、
「お、お帰りなさい、汐里さ――汐里…!」
どこか、他人行儀な態度。
それもかなり気にはなったが、説明するから二階へ行けという汐里の指令の元、琢磨は夕飯までゆっくりしてると言い残して、階段を上がり自室へと駆けこんだ。
さっさと着替えてしまっても良かったが、いつも帰宅時は汐里だったから、少し躊躇した。
「俺の勝手な想像だったらそう言ってくれ。ただいま、って言われた時、君なら何て返す?」
『――おかえり、って』
「だな。まぁ勝手な想像なのは確かなんだろうけど、違和感はあるよな。金持ちに貴族、再婚相手、目上の旦那。そんなところだ、『おかえりなさい』と返すのは。そうでなければ――」
バッグを置いてベッドに腰掛け、
「雇われ、ってとこか」と、溜息交じりにそう吐いた。
汐里は無言で頷き、何も言わなかった。
「随分と難しい境遇みたいだな。知音ちゃんには何とか話せたが」
美希、それに今感じた母親への違和感。
下手をすれば、悩みだけならまだまだありそうだ。
これだけの状況下にあって、それでも笑って強く自分を以って、前向きに考えて、それでいて周りにも気を遣って。自分でも言っていた通り、最悪話さないこともあった。いい友人に恵まれているということもあるのだろうが、それ込みで、汐里の強さだ。
抱えきれずに溢れた感情も、知音のお陰で零れた言葉も、どちらも汐里が一人で抱えて、抱えきれなくなって飛び出したものだ。
「まぁ、何だ。すげーいい奴だな、陸上さん」
『別に。それが私の普通だもん。人に話すのって、親友でもちょっとしんどいし。話すだけでも楽になるってよく聞くけど、私にとってあれは嘘』
「いや、それは俺も分かるぞ。受け入れてくれたらいいが、そうでないなら――そうでないなら、じゃあ言わない方がいい。言わないと抱えて、抱えると今度は自分がどんどんしんどくなってきて、じゃあ誰かに言おうかって思って――その、繰り返しだ」
『……仲村さんも、苦労してたんだね』
「今の君と比較すると劣るよ、各段に」
『人の悩みは、同じ種類でもその人によって大きさを変えるんだよ。仲村さんの言葉を借りるなら、それこそ、その人自身の人生。誰にも操作出来ないの』
汐里のそんな返しが意外も意外で、琢磨は苦笑した。
話を切り出したりする際、汐里はよく琢磨に問いかけていた。その度、琢磨が君の人生だからと諭していたのだが、それをまさか返される日が来ようとは。
琢磨の記憶が受け継がれているという話だったから、その感覚や考え方、性分なんかも少しずつ影響してきていたりするのだろうか。企業秘密だと老人は言っていたが、未だにそのカラクリは見当も付かない。
だが、互いに悪い気はしなかった。
琢磨は勘付いているらしかったが、だからといって話さない理由にはならないと、汐里は落ち着ける場所を探して一つ提案をした。
「おい待て、それだけは俺が落ち着かない」
『まだ何も言ってないでしょ?』
「何となく分かっちまうようになってたらしい――が、風呂だけは駄目だ。知音ちゃんにも殺されかねん」
『本人が良いって言ってるの。それに、ここだといつあの人が入って来るか分かんないし。お風呂が一番安心できる』
その言葉に、琢磨は何も突っ込みはしなかった。
「願わくば入れ替わって欲しいところではあるが、まぁそういうことなら…」
『うん。今日は別に、怒らないから』
それを良しとも出来ないが、断ることもままならない琢磨。渋々と受け入れると、着替えを揃えて部屋を出た。
「ずっと思ってたが、女子って何でこんなに薄っすい下着なんだ? これじゃあある意味、そういう趣向の奴らに狙われても可笑しくはないだろ」
『ちょ…! 触らないの! 誰も堪能して良いとか言ってないでしょ…!』
「だから殺意は隠せって。そうじゃなくて、単純な疑問だ」
『知らないわよ。それが普通なんだから、考えたって仕方ないことじゃない』
「仕方ない、か」
琢磨にはどうも、その言葉は言い訳のような気がしてならなかった。
いや、下着云々の話は置いておいて、普通だからという言い分が、昔からどこか引っかかっていたのだ。
普通だから変えない、普通だからそれに従う。思えば、そうじゃない人がいなければ、ファッショにせよものにせよ、何の変化もなかった訳だ。言ってしまうと、ちょっと変わった趣味の人やちょっと変態じみた人が居たからこそ、変化が成されているのである。
そこを無視して「普通だから」と置くのは可笑しいと、常々思っていたのだ。
『――っていうのも、聞こえてるのよね』
「おっと、そうだったか。でもな、結局そういうことなんだよ」
『何の話?』
「いやな。変わりたいって願わないと、何も進まないんだよ。さっきの君の意気込みのようにね」
琢磨がそう言うのは、帰宅途中の話だった。
立ち止まり、琢磨がそう指摘すると、
『寧ろ都合が良いかな。そのまま帰ってくれる?』
「わ、分かった」
都合が良いとは。その言葉に疑問を抱きながらも、琢磨は既に見慣れた門を通り抜け、扉を開けて家に入った。
靴を脱いで揃えて置いて、リビングの方へ顔を出した。
「ただいまー」
何のことも無くそう言うと、話しかけた相手である母親は、勢いよく振り返って、
「お、お帰りなさい、汐里さ――汐里…!」
どこか、他人行儀な態度。
それもかなり気にはなったが、説明するから二階へ行けという汐里の指令の元、琢磨は夕飯までゆっくりしてると言い残して、階段を上がり自室へと駆けこんだ。
さっさと着替えてしまっても良かったが、いつも帰宅時は汐里だったから、少し躊躇した。
「俺の勝手な想像だったらそう言ってくれ。ただいま、って言われた時、君なら何て返す?」
『――おかえり、って』
「だな。まぁ勝手な想像なのは確かなんだろうけど、違和感はあるよな。金持ちに貴族、再婚相手、目上の旦那。そんなところだ、『おかえりなさい』と返すのは。そうでなければ――」
バッグを置いてベッドに腰掛け、
「雇われ、ってとこか」と、溜息交じりにそう吐いた。
汐里は無言で頷き、何も言わなかった。
「随分と難しい境遇みたいだな。知音ちゃんには何とか話せたが」
美希、それに今感じた母親への違和感。
下手をすれば、悩みだけならまだまだありそうだ。
これだけの状況下にあって、それでも笑って強く自分を以って、前向きに考えて、それでいて周りにも気を遣って。自分でも言っていた通り、最悪話さないこともあった。いい友人に恵まれているということもあるのだろうが、それ込みで、汐里の強さだ。
抱えきれずに溢れた感情も、知音のお陰で零れた言葉も、どちらも汐里が一人で抱えて、抱えきれなくなって飛び出したものだ。
「まぁ、何だ。すげーいい奴だな、陸上さん」
『別に。それが私の普通だもん。人に話すのって、親友でもちょっとしんどいし。話すだけでも楽になるってよく聞くけど、私にとってあれは嘘』
「いや、それは俺も分かるぞ。受け入れてくれたらいいが、そうでないなら――そうでないなら、じゃあ言わない方がいい。言わないと抱えて、抱えると今度は自分がどんどんしんどくなってきて、じゃあ誰かに言おうかって思って――その、繰り返しだ」
『……仲村さんも、苦労してたんだね』
「今の君と比較すると劣るよ、各段に」
『人の悩みは、同じ種類でもその人によって大きさを変えるんだよ。仲村さんの言葉を借りるなら、それこそ、その人自身の人生。誰にも操作出来ないの』
汐里のそんな返しが意外も意外で、琢磨は苦笑した。
話を切り出したりする際、汐里はよく琢磨に問いかけていた。その度、琢磨が君の人生だからと諭していたのだが、それをまさか返される日が来ようとは。
琢磨の記憶が受け継がれているという話だったから、その感覚や考え方、性分なんかも少しずつ影響してきていたりするのだろうか。企業秘密だと老人は言っていたが、未だにそのカラクリは見当も付かない。
だが、互いに悪い気はしなかった。
琢磨は勘付いているらしかったが、だからといって話さない理由にはならないと、汐里は落ち着ける場所を探して一つ提案をした。
「おい待て、それだけは俺が落ち着かない」
『まだ何も言ってないでしょ?』
「何となく分かっちまうようになってたらしい――が、風呂だけは駄目だ。知音ちゃんにも殺されかねん」
『本人が良いって言ってるの。それに、ここだといつあの人が入って来るか分かんないし。お風呂が一番安心できる』
その言葉に、琢磨は何も突っ込みはしなかった。
「願わくば入れ替わって欲しいところではあるが、まぁそういうことなら…」
『うん。今日は別に、怒らないから』
それを良しとも出来ないが、断ることもままならない琢磨。渋々と受け入れると、着替えを揃えて部屋を出た。
「ずっと思ってたが、女子って何でこんなに薄っすい下着なんだ? これじゃあある意味、そういう趣向の奴らに狙われても可笑しくはないだろ」
『ちょ…! 触らないの! 誰も堪能して良いとか言ってないでしょ…!』
「だから殺意は隠せって。そうじゃなくて、単純な疑問だ」
『知らないわよ。それが普通なんだから、考えたって仕方ないことじゃない』
「仕方ない、か」
琢磨にはどうも、その言葉は言い訳のような気がしてならなかった。
いや、下着云々の話は置いておいて、普通だからという言い分が、昔からどこか引っかかっていたのだ。
普通だから変えない、普通だからそれに従う。思えば、そうじゃない人がいなければ、ファッショにせよものにせよ、何の変化もなかった訳だ。言ってしまうと、ちょっと変わった趣味の人やちょっと変態じみた人が居たからこそ、変化が成されているのである。
そこを無視して「普通だから」と置くのは可笑しいと、常々思っていたのだ。
『――っていうのも、聞こえてるのよね』
「おっと、そうだったか。でもな、結局そういうことなんだよ」
『何の話?』
「いやな。変わりたいって願わないと、何も進まないんだよ。さっきの君の意気込みのようにね」
琢磨がそう言うのは、帰宅途中の話だった。