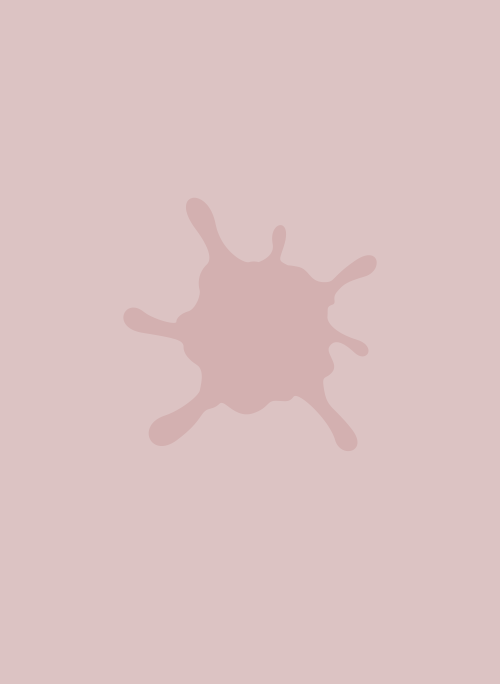「今回だけは見逃してやるよ。たまちゃんのお願いだからねえ、聞かないわけにはいかないさ」
忌々しい目を侍に向けるが、口元は笑っている。
「それと最後にあと一つだけ。侍さんはどうしてメロンソーダが好きなんですか? いつも持ってるけど、それはどうして?」
「なんだお前、これから逝くってえのにまだそんなこと言ってんのかい。そんなに気になるかい? 仕方ねえ、じゃ教えてやるよ。今からほんの少し前の昭和の時代にな、一時だけどすんごく流行ったんだよ。ぜんぜんメロンの味なんかしないけどな、このよくわからん緑色の液体にバニラアイスが溶けたときの味に衝撃を受けたんだよ」
侍が大きく頷いた。
「それだけ?」
「……なんだよ、美味いもんは美味いんだから別にそれでいいじゃねえか」
好きな理由なんかそんなもんしっかりなくてもいいだろうが。と本気になってもんくを言う。
そんなことはお構いなしとたまこがぱあっと明るい顔になる。昭子もまんざらでもない様子でにたにたしていた。
「さ、もういいだろう。早く行け。太郎は俺と違って待っちゃあくれねえぞ。あいつはそういうとこ気が利かねえからな」
太郎の方を急いで向けば、痛みに耐えられずじたばた暴れまわって悲鳴を上げ続ける司が目に入る。司の血まみれになった頭を鷲掴みにしたまま真っ暗な穴の中に引きずり去っていくところであった。
そのすぐ側で、瑞香がたまこをじっと待っていた。こちらを向いて無表情で立っている。
たまこはもう一度昭子と侍に目を向けると、三人で同時に大きく頷きあった。
お互いに今までで一番の笑顔を見せ合い、たまこは瑞香の元へ走って行った。
瑞香とたまこは太郎の後ろにべたりと張り付いたまま、闇の奥底へと消えていく。
後にしばらく残ったのは、司の張り裂けんばかりの恐怖に打ちのめされる悲鳴と何人もの女の甲高い笑い声のみであった。
忌々しい目を侍に向けるが、口元は笑っている。
「それと最後にあと一つだけ。侍さんはどうしてメロンソーダが好きなんですか? いつも持ってるけど、それはどうして?」
「なんだお前、これから逝くってえのにまだそんなこと言ってんのかい。そんなに気になるかい? 仕方ねえ、じゃ教えてやるよ。今からほんの少し前の昭和の時代にな、一時だけどすんごく流行ったんだよ。ぜんぜんメロンの味なんかしないけどな、このよくわからん緑色の液体にバニラアイスが溶けたときの味に衝撃を受けたんだよ」
侍が大きく頷いた。
「それだけ?」
「……なんだよ、美味いもんは美味いんだから別にそれでいいじゃねえか」
好きな理由なんかそんなもんしっかりなくてもいいだろうが。と本気になってもんくを言う。
そんなことはお構いなしとたまこがぱあっと明るい顔になる。昭子もまんざらでもない様子でにたにたしていた。
「さ、もういいだろう。早く行け。太郎は俺と違って待っちゃあくれねえぞ。あいつはそういうとこ気が利かねえからな」
太郎の方を急いで向けば、痛みに耐えられずじたばた暴れまわって悲鳴を上げ続ける司が目に入る。司の血まみれになった頭を鷲掴みにしたまま真っ暗な穴の中に引きずり去っていくところであった。
そのすぐ側で、瑞香がたまこをじっと待っていた。こちらを向いて無表情で立っている。
たまこはもう一度昭子と侍に目を向けると、三人で同時に大きく頷きあった。
お互いに今までで一番の笑顔を見せ合い、たまこは瑞香の元へ走って行った。
瑞香とたまこは太郎の後ろにべたりと張り付いたまま、闇の奥底へと消えていく。
後にしばらく残ったのは、司の張り裂けんばかりの恐怖に打ちのめされる悲鳴と何人もの女の甲高い笑い声のみであった。