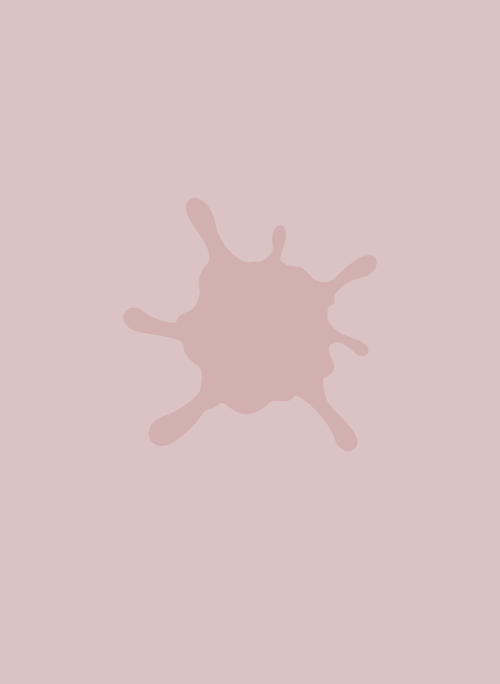侍は初めて集まったときにこのこぢんまりとした家を目にして、なんだこれは、俺の実家はこんなちんけな家じゃあないぞ。大店だったって言ったじゃねえか。ともんくを言ったが、「三人しかいないんだ。これで十分だろう。きゃんきゃんとよく吠える犬だねえ」と昭子に切り捨てられた。
太郎は、
「俺は料理が得意だから、なんでも作ってやるぜ」と出刃包丁をぎらつかせた。侍はそれを見て、昔を思い出し、襟元で首を隠したりもした。これは刃物を見るとついついやってしまう癖であった。昭子は、「料理を作ってくれるのは嬉しい。太郎の料理はすこぶる美味いからねえ。でも、作るのはあたしらが食べられる物だけにしとくれよ。それじゃ、あたしは気味の悪い霊が来たら迷わず凍らせてやるさ。それに、女の霊が来たときに綺麗な女がいたほうが何かと安心もするだろう」
と自分の役割を決めた。
「それじゃあ、俺が彷徨える霊を見つけて、その時が来たらここに来られるように細工してくるぜ。そいつらがどうやって死んだのかを肴に一杯やろうじゃあないか」
と侍が胸を張れば、あんたもいい趣味をしているねえ、と昭子と太郎に気に入られて晴れて仲間になった。
そんな馴れ初めがあっての三人とこの家なのであった。
太郎は、
「俺は料理が得意だから、なんでも作ってやるぜ」と出刃包丁をぎらつかせた。侍はそれを見て、昔を思い出し、襟元で首を隠したりもした。これは刃物を見るとついついやってしまう癖であった。昭子は、「料理を作ってくれるのは嬉しい。太郎の料理はすこぶる美味いからねえ。でも、作るのはあたしらが食べられる物だけにしとくれよ。それじゃ、あたしは気味の悪い霊が来たら迷わず凍らせてやるさ。それに、女の霊が来たときに綺麗な女がいたほうが何かと安心もするだろう」
と自分の役割を決めた。
「それじゃあ、俺が彷徨える霊を見つけて、その時が来たらここに来られるように細工してくるぜ。そいつらがどうやって死んだのかを肴に一杯やろうじゃあないか」
と侍が胸を張れば、あんたもいい趣味をしているねえ、と昭子と太郎に気に入られて晴れて仲間になった。
そんな馴れ初めがあっての三人とこの家なのであった。