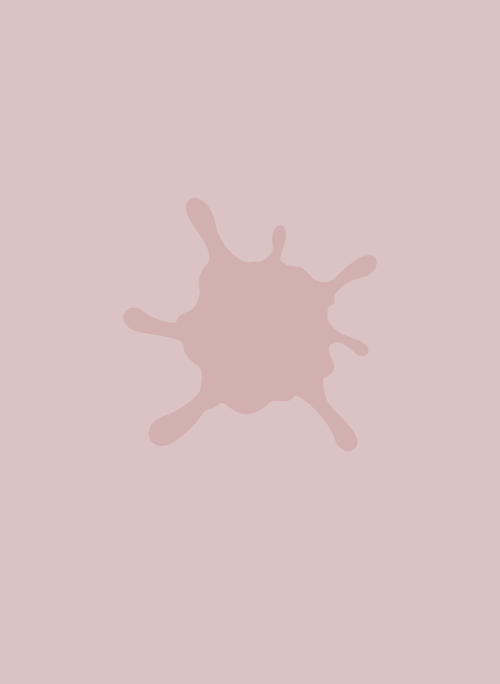そんなこんなで数年の後、再度実家のあった三叉路に戻ってきたときに、昭子と太郎に偶然ばったり出会ったのである。
昭子と太郎もこの世に飽き飽きしていた頃であった。
そこに人見知りをしない侍が一つ試しに挨拶を投げかけてみた。うかつにも昭子と太郎は侍の方を向いてしまったのだ。
侍は二人には己が見えている。久しぶりに感動し、話しかけてきたものだから鬱陶しい。半ば面倒臭がる二人の周りをくるくる回り、あの手この手で説得し、三人で何かしようという話に引き込んだのであった。このとき既に二人は人じゃあないということを侍は知っていた。
昭子は紅色の綺麗な着物を着てはいるが、雪のように白く、同じように真っ白い目を見りゃわかるが、見たまま、雪女そのものだったし、太郎は粋な格好をしていたが、後ろに隠すことなくオレンジ色のよく燃えている炎を纏っていた。
実は、侍は太郎の知らぬうちに全国あちこちで太郎に何度も出くわしていた。
太郎の仕事っぷりにはそれはそれは身震いをするほどの怖さがあったのを覚えている。侍が見た太郎は、長い爪を死体に食い込ませ、死者を頭から食いちぎっていたのだ。
悪事はしてきたが、太郎に出くわさなくて良かったと胸を撫で下ろしたこともあった。
そんな恐ろしい太郎が今、己の目の前にいるのだ。この機会を逃すまい。好奇心いっぱいだった。
なんとかしてこの二人の仲間に入りたい。そう思って、侍お得意のあることないこと面白おかしく最大限に膨らまして話し始めたのだ。
昭子と太郎もこの世に飽き飽きしていた頃であった。
そこに人見知りをしない侍が一つ試しに挨拶を投げかけてみた。うかつにも昭子と太郎は侍の方を向いてしまったのだ。
侍は二人には己が見えている。久しぶりに感動し、話しかけてきたものだから鬱陶しい。半ば面倒臭がる二人の周りをくるくる回り、あの手この手で説得し、三人で何かしようという話に引き込んだのであった。このとき既に二人は人じゃあないということを侍は知っていた。
昭子は紅色の綺麗な着物を着てはいるが、雪のように白く、同じように真っ白い目を見りゃわかるが、見たまま、雪女そのものだったし、太郎は粋な格好をしていたが、後ろに隠すことなくオレンジ色のよく燃えている炎を纏っていた。
実は、侍は太郎の知らぬうちに全国あちこちで太郎に何度も出くわしていた。
太郎の仕事っぷりにはそれはそれは身震いをするほどの怖さがあったのを覚えている。侍が見た太郎は、長い爪を死体に食い込ませ、死者を頭から食いちぎっていたのだ。
悪事はしてきたが、太郎に出くわさなくて良かったと胸を撫で下ろしたこともあった。
そんな恐ろしい太郎が今、己の目の前にいるのだ。この機会を逃すまい。好奇心いっぱいだった。
なんとかしてこの二人の仲間に入りたい。そう思って、侍お得意のあることないこと面白おかしく最大限に膨らまして話し始めたのだ。