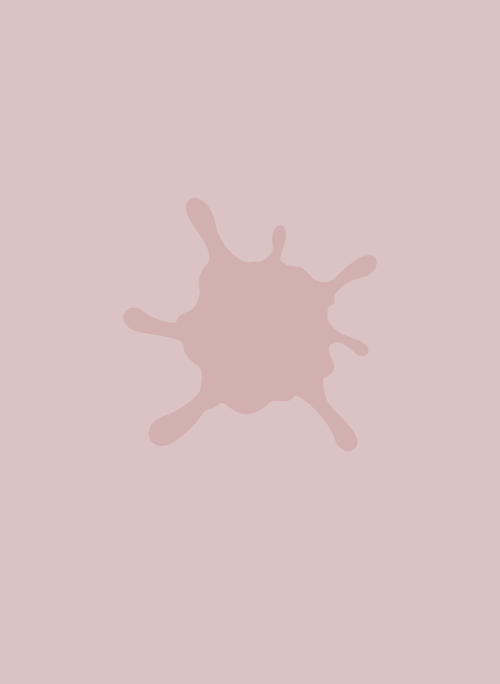とはいえ、もしかしたら何かいるのかと侍はどこぞに子の霊がいるのかどうか辺りを見回してみたけれど、やはり侍の他に霊らしきものはいなかった。
むしろ、霊である侍すらこの老婆にはまったく見えていないのである。
期待した希望が消え、早々に老婆の家を後にした侍は、今一度三叉路に引き寄せられるように戻ってみた。
そして、実家がどうなったか聞く術がもうない。知り合いもいなくなっている。親戚一同はこの辺にしかいなかった。
その辺りがごっそりなくなっているんだ。だから聞くな。溢れ出る涙を指で拭い、このことは忘れるんだ。と己に叩き込んだ。
根拠のない『大丈夫』にたかをくくっていた己に非がある。これは己の失敗であると強く言い聞かせた。ところで。
これはまいった。とお茶目におでこを叩いたのである。
こうなっちまっちゃあどうしようもねえ。うん。仕方がねえ。と開き直った。
それならば旅を続けても誰にももんくは言われやしないだろう。よし。
今までの旅路で特に気に入ったところを再訪するという旅を計画し、旅路についたのだ。上は青森、下は山口までの本州に絞って行動したという、やはり死んでからも根っからのどうしようもない楽観主義を地にいく放蕩息子なのであった。
むしろ、霊である侍すらこの老婆にはまったく見えていないのである。
期待した希望が消え、早々に老婆の家を後にした侍は、今一度三叉路に引き寄せられるように戻ってみた。
そして、実家がどうなったか聞く術がもうない。知り合いもいなくなっている。親戚一同はこの辺にしかいなかった。
その辺りがごっそりなくなっているんだ。だから聞くな。溢れ出る涙を指で拭い、このことは忘れるんだ。と己に叩き込んだ。
根拠のない『大丈夫』にたかをくくっていた己に非がある。これは己の失敗であると強く言い聞かせた。ところで。
これはまいった。とお茶目におでこを叩いたのである。
こうなっちまっちゃあどうしようもねえ。うん。仕方がねえ。と開き直った。
それならば旅を続けても誰にももんくは言われやしないだろう。よし。
今までの旅路で特に気に入ったところを再訪するという旅を計画し、旅路についたのだ。上は青森、下は山口までの本州に絞って行動したという、やはり死んでからも根っからのどうしようもない楽観主義を地にいく放蕩息子なのであった。