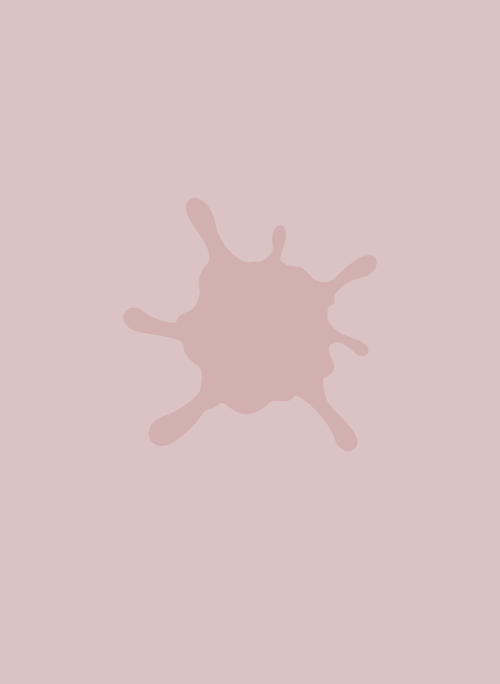そこで目にした光景に侍はへなへなとその場に尻をつけることになった。
目の前には懐かしい実家、大繁盛をしているはずであろう大店があるはずであった。見覚えのある立派な大店が佇んでいるはずであった。しかしながら目にしているところには懐かしい大店は跡形もなく無いのだ。
大店があったはずの場所は、なんと、道路に変わり果てていたのである。
丁度三叉路に広がった道に変わり果てていた。
自分の生まれた家がまっさらになって消えていた。
いつからこうなったのか、まるで検討もつかない。
親戚縁者がどこぞにいるのか聞きたくとも、なぜだか聞きたくないという気持ちも相まっていた。
そのことにはふんわりと布を被せて見ないふりをしてきたのだ。嫌なことを今更聞きたくない。悲しくなる話なら聞かなきゃ無いと同じだ。
当初はまだ人には自分が見えないし、気づいてもらえないし話しかけても帰ってくることばはなかった。
ここは一つ期待はしていないが、イタコと呼ばれる死者と話のできるという胡散臭い商売をしている老婆のところに出向いてみた。
しかし、目の前で繰り広げられていたのは、眉唾を絵に描いたようなお粗末なものであった。
子を幼くして無くした母親が我が子と話したいとやってきていた。
イタコの老婆に乗り移ったという子の霊と話をしているというものであった。
今目の前にいる侍にすら気づいていない老婆の目は、騙くらかしてやろうという悪の気持ちにギラついていた。
侍はそんな老婆を残念な目で見、子を失った母親に目を戻すと、その女はたいそう金持ちの妻であろうことがわかる身なりをしていた。
生前の己と重ね合わせ、なるほどと一つ大きく頷いた。
泣きながらに話す女は、老婆の嘘八百をまるっきり信じ込んでいる風であった。
目の前には懐かしい実家、大繁盛をしているはずであろう大店があるはずであった。見覚えのある立派な大店が佇んでいるはずであった。しかしながら目にしているところには懐かしい大店は跡形もなく無いのだ。
大店があったはずの場所は、なんと、道路に変わり果てていたのである。
丁度三叉路に広がった道に変わり果てていた。
自分の生まれた家がまっさらになって消えていた。
いつからこうなったのか、まるで検討もつかない。
親戚縁者がどこぞにいるのか聞きたくとも、なぜだか聞きたくないという気持ちも相まっていた。
そのことにはふんわりと布を被せて見ないふりをしてきたのだ。嫌なことを今更聞きたくない。悲しくなる話なら聞かなきゃ無いと同じだ。
当初はまだ人には自分が見えないし、気づいてもらえないし話しかけても帰ってくることばはなかった。
ここは一つ期待はしていないが、イタコと呼ばれる死者と話のできるという胡散臭い商売をしている老婆のところに出向いてみた。
しかし、目の前で繰り広げられていたのは、眉唾を絵に描いたようなお粗末なものであった。
子を幼くして無くした母親が我が子と話したいとやってきていた。
イタコの老婆に乗り移ったという子の霊と話をしているというものであった。
今目の前にいる侍にすら気づいていない老婆の目は、騙くらかしてやろうという悪の気持ちにギラついていた。
侍はそんな老婆を残念な目で見、子を失った母親に目を戻すと、その女はたいそう金持ちの妻であろうことがわかる身なりをしていた。
生前の己と重ね合わせ、なるほどと一つ大きく頷いた。
泣きながらに話す女は、老婆の嘘八百をまるっきり信じ込んでいる風であった。