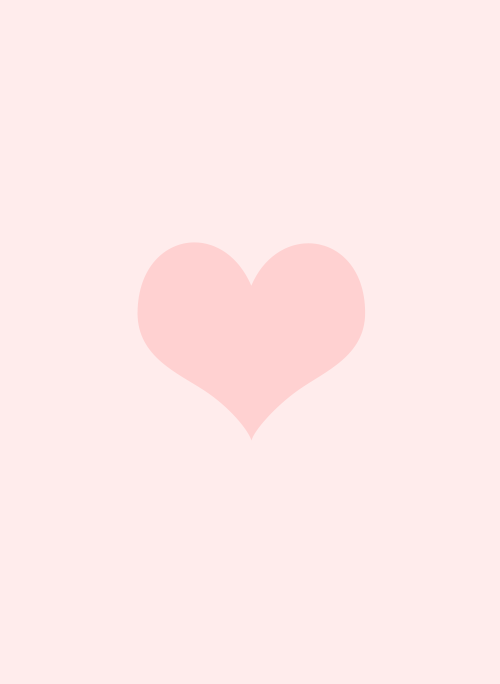真尋ったら、束縛って。
そんな縛ってまで喋ろうとは思ってないよ。
だいたい今の真尋を縛るにも触れることさえできないのだから縛れないし。
そんなことしなくても真尋なら聞いてくれるでしょう。
細めていた目をしっかりと開けると、一瞬、確かに彼女が透けていて思わず眉毛が垂れ下がった。
そんなわたしに気づいたのか、真尋はからりと笑ってみせた。
『言わなくても、もうわかってるよ』
くるり、紺色のスカートを翻して回る彼女。
わかってる、か。
そりゃあね、そうだよね。
長いこと一緒の時間を過ごして来たんだから、そりゃそうだ。
じゃあ改まって言う必要はないか。
なんと言ったって、わたしたちは親友なのだから。
『ほら、だから真尋のことはいいから。いつでも来てくれたら今宵とこうやってお話できるし』
「えっ、ほんと?」
『うん。だからさ、早く行きなよ。待ってるんでしょ、気になるんでしょ』
ふわり、彼女の髪が揺れる。
どこからか風が吹いたわけでもないのに。
それがまた儚くて、綺麗で、少し泣きそうになって下を向いて。
そうしたら、頭に何かを感じて。
真尋の微笑みにまた泣けてきて。