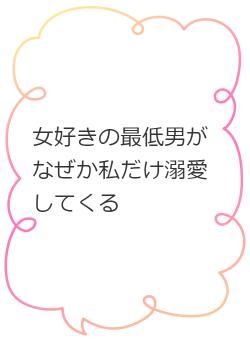木のスプーンで少しだけお粥を救い上げ、口に運ぶ。
喉を過ぎる瞬間痛みが走る。
熱が高いから余計に喉の痛みも強いのかもしれない。
「はい、これ薬」
お母さんが手の上に3粒の白い錠剤を乗せてくれる。
あたしはそれを口に含み、水で流し込んだ。
そのまま倒れるように横になり、目を閉じる。
薬を飲んだことを確認したお母さんはホッとしたように息を吐き出し、そのまま部屋を出て行ったのだった。
喉を過ぎる瞬間痛みが走る。
熱が高いから余計に喉の痛みも強いのかもしれない。
「はい、これ薬」
お母さんが手の上に3粒の白い錠剤を乗せてくれる。
あたしはそれを口に含み、水で流し込んだ。
そのまま倒れるように横になり、目を閉じる。
薬を飲んだことを確認したお母さんはホッとしたように息を吐き出し、そのまま部屋を出て行ったのだった。