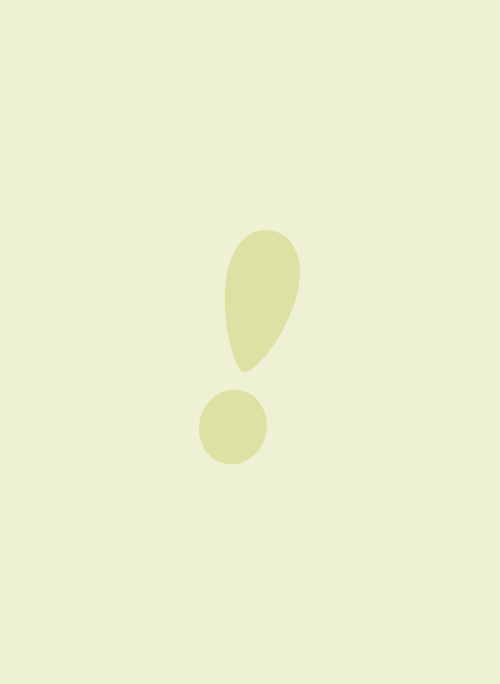「へ、陛下っ! ごめんなさい、わたくし……」
「眠いならべつに寝台を使ってくれてもよかったのに。座ったままでは首が痛くならないか」
そういう俺もよくやるんだけどな、と、アルザは笑う。
その笑みに、なぜだかどこか懐かしい感じがして、そんな自分にリーラは驚いた。
奇妙な気持ちのままアルザに勧められた茶を口にした。
ちらりと窓の外に目を向けると、暗闇の中にぽつぽつと遠い燭台の火が見える。
一部の見張りの兵以外のだれもが寝静まった夜中の静けさの中に、火が揺らめく。
「……陛下は、いつもこんな夜遅くまで?」
「そうだな。今日は姫が話があるというから早く切り上げたかったんだが、ストロック伯から新たな献言書が届いてな。目を通していたら遅くなった」
ストロック伯、という名前は知っていた。
昼間にレグナムが言っていたからだ。
小さな島々からなる領土を治める、――ただ二つのマナンに染まらぬ伯領のうちの一つ。
「それで、相談したいことというのは、……やはり婚礼の儀のことか?」
すこし困ったような笑みを浮かべて、アルザが言う。
もちろん最初はそのつもりだった。――けれど。
「いいえ、陛下」