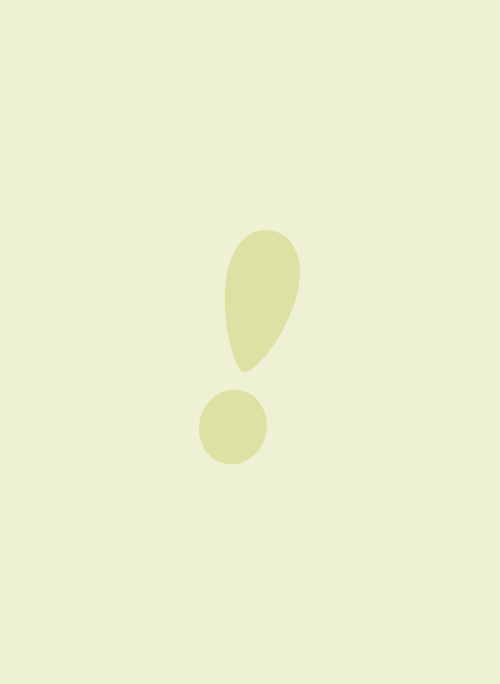「すみません、言い方が悪かったですね。殿下の自然で隙のない立ち振る舞いは賞賛に値します。
他国の姫でありながら、これからウィオンの政治の中枢に身を置くあなたに、その能力はどうしても必要なものだ。純粋に、すごいと思います」
本当ですよ、とカインは言って笑った。
「けど、あなたはもうウィオンの王妃なんだということに、もうすこし自信を持ってほしいんです」
「自信……?」
「はい。周りの空気に敏感なのはあなたの美点だ。けど、空気がどうあれ、あなたは陛下の妃となるべくしてウィオンに来て、陛下はわざわざあなたを港まで迎えに行き、あなたを受け入れられた。
政務が忙しくても、暇を見つけて顔を出したり、側近のレグナム様にあなたの様子を見に行かせている。あなたを気にかけている。違いますか?」
「違わ……ない、わね」
「でしょう? たとえ婚礼の儀がまだだとしても、陛下が否と言わなければあなたは王妃になるのです。
今のところ、陛下は否とは言っていない。言う気配もありませんよね。あなたが不安で疑心暗鬼になっているだけで。違いますか?」
「……いいえ。違わない」