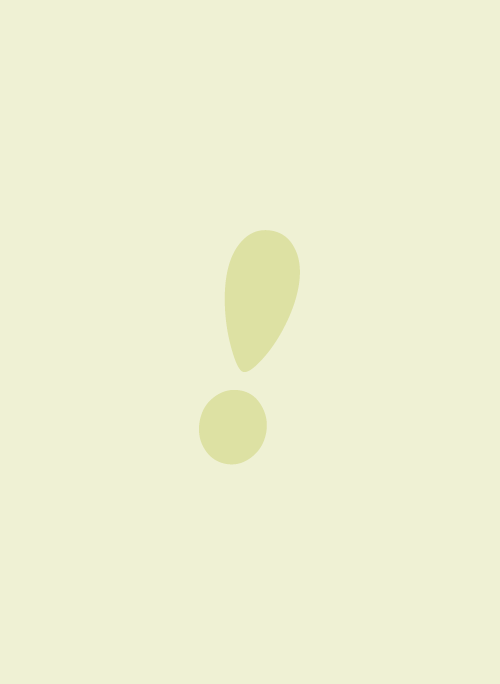まさか見抜かれていたとは思わず反応できずにいるリーラにかまわず、カインは続ける。
「そういう小細工は、他ならぬ殿下ご自身が、ご自分をあくまで“シュタインの姫”だと思っているからじゃないですか?」
図星だった。
リーラ自身も意識してはいなかったが、ウィオンの王妃として王宮の者に受け入れられたいと思っていながら、シュタインの姫の立場を崩さなかったのは自分自身だ。
にこにこと穏やかで、どこかふわふわした雰囲気のあるカインに、これほど鋭く指摘されるとは思わなかった。
思わなかった自分が恥ずかしかった。
政治と切り離された場だからといって、いや、だからこそ、神官たちは微妙な立ち位置から国の中枢に関わっている。
リーラの下心が神官にわからないと思うのは、あまりにも神官たちを下に見すぎている。
羞恥でみるみる顔が熱くなっていく。
リーラは立ち上がって頭を下げた。
「……ごめんなさい。わたくし、あなたたち神殿の者たちを愚弄するような真似をしたわね。非礼を詫びるわ」
ごめんなさい、ともう一度言うと、カインは驚いたように後ずさった。
「あぁ、すみません。責めてるわけじゃないんです!」
またもや思いがけない言葉に、リーラが顔を上げると、カインは慌てふためいたようにおろおろしていた。