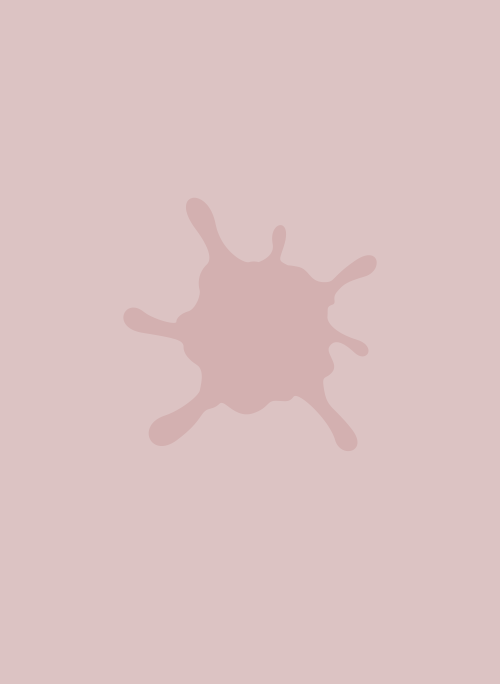そのうちに男の方が死んで、死体が自分の上に覆い被さる光景を目の前で見て、女は狂乱した。
私はそれを眺めながら、先に殺した男の頭を撫でていた。
「二人、足さないと」
ぼそっと呟いたことばはこの少年の耳に届いていて、作業をしながら口元だけをにっと、真横に伸ばした。
「もっと他にも面白いことがあるって言ったらどうします?」
こいつは私に視線をよこさずに慣れた手つきで片付けながらそんなことを言った。
もっと楽しいやりかたがあるってことだ。
「アユミさんの会いたがっている人は、そこのレベルにいるんです」
「レベル?」
「気にしないでください。そこへ行ってみたいとは思いませんか?」
「行きたい」もちろん行きたい。行ってみたい。
「それでは、この残りの二人で充分遊んでからそこへ行くということで、いいですね」
「ええ」
楽しもう。こいつらを思うままに楽しんで、それからだってぜんぜん遅くない、