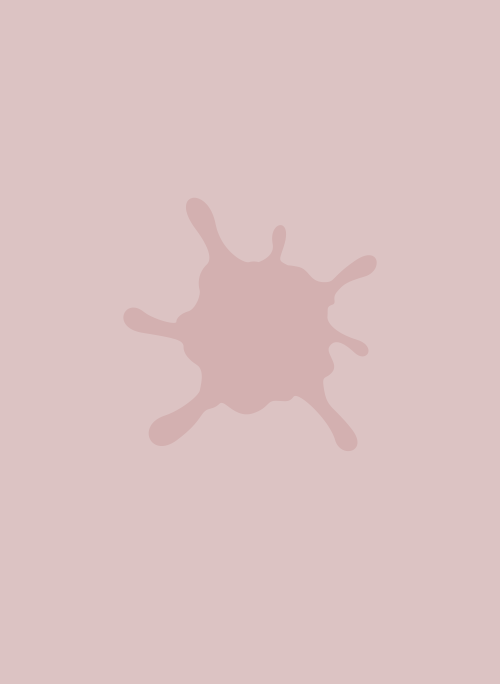動かなくなった彼の体が朽ち果てる前に、服を脱がせ、きれいに洗った。
舌と手のひら、足の裏を切り取り、保存用の袋に入れた。
その袋の中に、塩、昆布、ホワイトペッパー、ガーリックなどをよく混ぜ合わせ冷蔵庫に入れる。
1週間ほど寝かせることで肉と皮は柔らかくなる。
その間に用意した竹串で彼の腹をズブッと刺して腹の脂を抜く。
宝石のようにネロネロと輝く黄色いとろっとしたものが竹串を伝って流れ出る。それを透明のボールに溜め込む。
彼の体の中から出していいものはこの脂のみだ。他のものが流れ出るのを防ぐために太い針と太い糸で彼の瞼、鼻の穴、口、肛門をきつく縫い付けた。
最後に脂を取りきった腹の穴を綺麗に閉じた。
人を縫うあの感覚が手に脳に神経に残っている。ぷちっと皮を破る音、肉を突き刺したときのあの高鳴り。
夢中になって針を落とした。
改造した巨大なドラム缶は彼が生前に用意したものだ。その中に膝を折った状態で詰め込んだ。前処理としてちゃんと膝の後ろと腿のつけねを深く切っておいた。
死んだ人間は以外にも重くてその作業はなかなか手間のかかるものだった。
汗だくになった。
自分の手が愛しい彼の脂まみれで滑り、その脂と血のにおいで嗅覚はとっくに麻痺していた。
「……つかれる」
自分でも驚いたことに、最初のことばはこれだった。
無論、彼からはなんの返事もない。
顔は見られたものじゃなかった。縫い付けられた顔はひしゃげ、鼻は潰れ、魅力的だった唇は歪(いびつ)に歪んでいた。
原型を留めていない。
もうコレは私の彼氏じゃない。