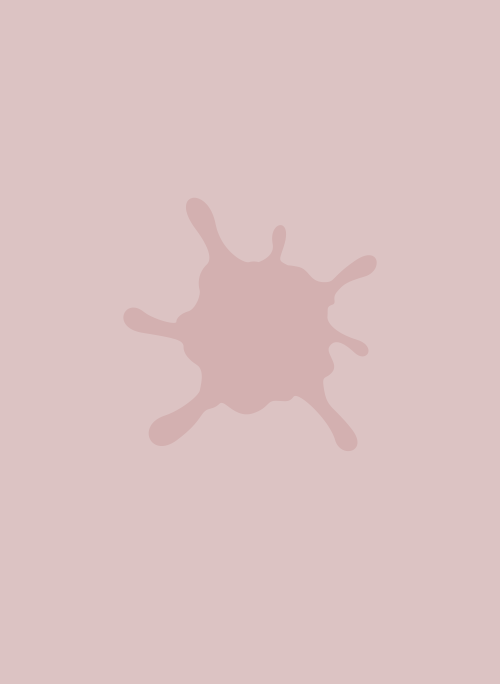「ねえ、何でこの人こんなに苦しそうなの?」
「それはね、まだ死んでないからよ」
「苦しくないの?」
「苦しいわよ」
「どうしたら? どうしたら楽にしてあげられるの?」
「……楽にしてあげたい?」
「してあげたい!」
「そう。じゃあ、これをこの男の喉深くに差し込んでごらん」
「これって、ナイフ?」
「そうよ。こいつはもう意識は無いのよ。でもね、まだちゃんと死ねてないの」
「……」
「ほら、早くやってごらん」
近寄りたくない雰囲気と笑みを顔に浮かべながらこの女は私にそう言った。
私はまだほんの子供だった。7つか8つか、だいたいそのくらいだったと思う。
私の手の中にはこの女から渡された銀色に輝く冷たいナイフが握りしめられている。
これを目の前で仰向けに倒れている男の喉に突き刺せば、きっと苦しまずに死ねるんだと思った。
死ぬということがよく分かっていなかったのもあって、とにかく死んだら苦しいことから逃げられて、また明日には元気になっているものだ。と、そう私は思っていた。