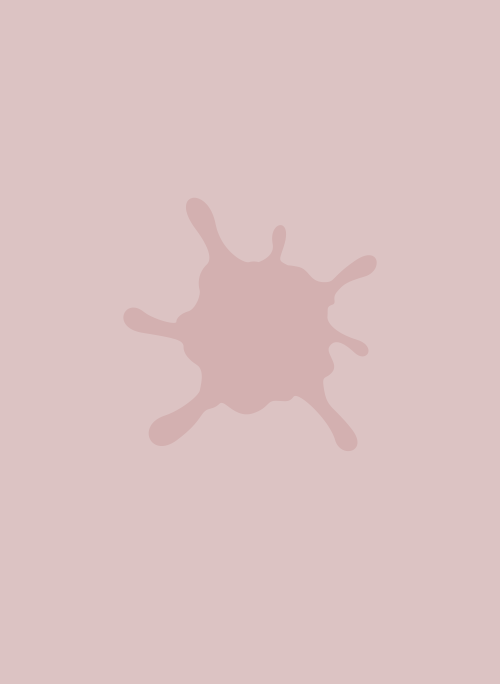「僕はね、今までに四人を食べてきた。みんな味が違うんだよ。苦味のきついものもあったし、柔らかく甘いものもあった。四人は全員今も僕の中で生きている。その四人も過去に何人か食ってきてるだろう。いいかい、僕が君に教えることをしっかりと覚えておくんだよ」
そんなことを言っていた。彼の言ったことばをひとつひとつ思い出しながら焼き上がった舌を奥歯で噛み潰した。
味が染み込んでいて柔らかくまろやかだ。
手のひらは焦げ付くくらいまで焼くと苦味が抜けて香ばしくなる。
「いいかい、燻す過程で独特な臭いが出てくるから周りの人が怪しんで何か噂をたてるかもしれない。はっきり言ってやっていいよ」
「え。それって」
「肉の燻製を作っている。と、本当のことを言えばいい。それが牛や豚やソーセージじゃなくて、人間ってだけの話だ。何の肉かさえ言わなければ嘘じゃない」
彼はそんなことを心配していたけれど、そんなこと全然気にしなくてよかったんだ。
だって私は彼のアパートの屋上にいる。5階建てのアパートの屋上だ。ここからなら煙は上に向けて上がって行くだけだ。誰にも気付かれない。気付くことはない。