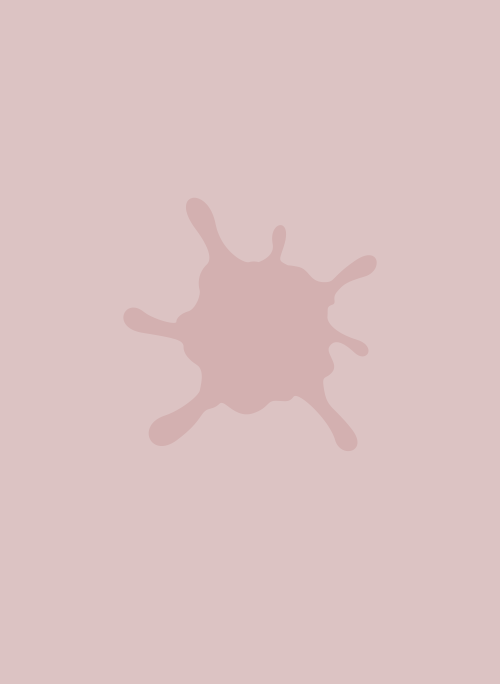「さあ、それから君はどうするんだっけ?」
彼は楽しむように私に笑いかけた。
「それから、1時間ほどドラム缶を開けて空気に晒します。そのあと冷めきらないうちにまた燻します」
「いいね。そうだ。1回目では僕の中までちゃんと火が通らない。2回目でようやく深部まで火が通るんだ。そうしたら?」
「そうしたら、ドラム缶からアナタを外します。詰められたままの格好で固まっています。まだ熱いうちに、首、両腕、両脚を切り離します」
「残酷だね、君は」
彼は嬉しそうに笑っていた。
「……私はすぐにアナタの顔を食べます」
「そうだ」
「縫った瞼と鼻、唇をナイフで切り裂き、頭の真ん中にナイフを落とします。そして皮を剥ぐ」
「それから?」
「髪の毛は捨て、ぱりぱりになった顔の皮に頬の肉や脳味噌を巻いて食べる」
「それで」くくくっと笑ったその口許には涎が光っていた。
「それで、首を上に向けたので目玉は下に落ち窪み、溶けているはずです。だから、眼窩に残った滑りをしゃぶりとる」
「それで、僕は君のその瞳とひとつになれる」
「……はい」