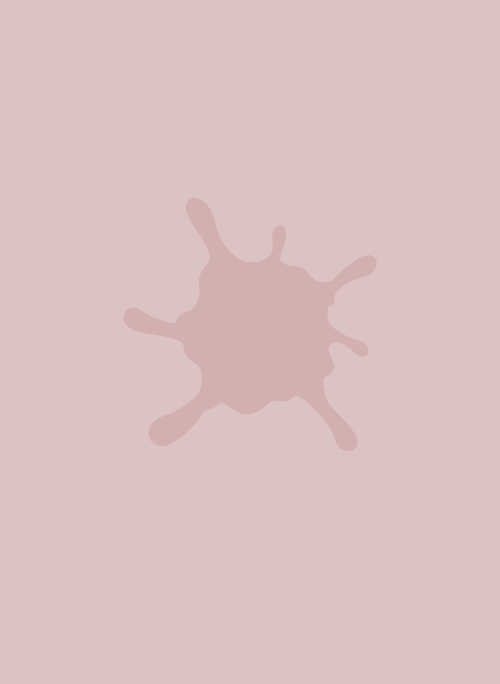「なんで…?どうして、芹沢さんがいるの…?」
私の問いかけに、
にこっちは目を見開いた。
父も、母もいなかった病室に、
ただ、にこっちが1人だけ。
あたしは、ベッドから重たい身体を起こす。
少し、手首が傷んだ。
「どうしてって……そんなの、友達だからに決まってるじゃん…。心配だから、いなくなってほしくないから…」
「友達……?意味わかんない」
本当に、意味がわからなかった。
友達?
友達って?
友達って、なんですか?
にこっちは、
あたしの手を握り返した。
今までに経験したことのない、
他人の温もり。
「難しいよね。友達って……。私も、よく分からないけど、だけど、ずっと、見てきたよ。希望ちゃんが頑張ってるところ。でもね、いつも寂しそうだった。ずっと……1人…」
「意味わかんない。芹沢さんに、なにが分かるの…?」
「分かる。分かるよ。だって、いつも先を行く希望ちゃんを見てきたから。ねぇ、希望ちゃん」
にこっちの腕が、あたしの背中に回る。
小さな身体が、あたしを包み込んだ。