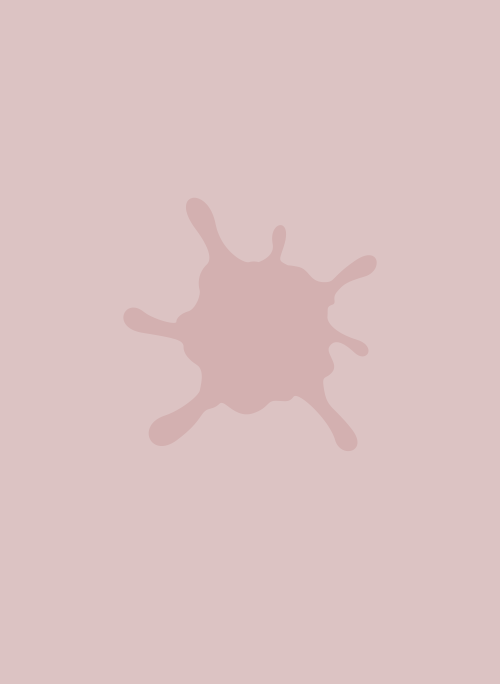家に帰ってからも、
彼女のことが忘れられなくて、
ずっと頭にちらついていた。
彼女も、僕に話しかけるなんて、
よほど物好きだと思う。
みんなは、僕のことを
" 障がい者 "と呼ぶ。
もちろん、間違っていることじゃないし、怒ったりはしないけど、
僕は区別されているようで、
その言葉が好きじゃない。
だけど、彼女は、虹心は、
少し驚くだけで、
普通に話してくれた。
帰り際、手を振ってくれた。
僕には、それすらも嬉しく感じられた。
小さい時から、
僕の周りは無関心で溢れていた。
話しかけてきたクラスメイトも、
僕の障がいを知ると離れていく。
だから、僕は、
嬉しかったんだ。
虹心が、初めてだったから。
でも、期待はしない。
しちゃいけない。
それで、何度も裏切られてきた。
僕は教科書を閉じると、
ゆっくり目を閉じた。