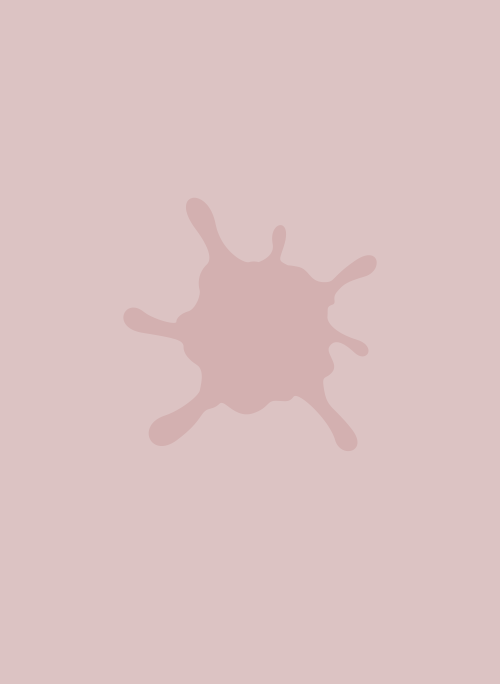「にこっちー、なかなかやるねぇ〜」
食事をリビングへ配膳している時、
希望がニヤニヤと肘で突いてきた。
お母さんに、私が明君のことを好きだと暴露したことを言っているのは確かだった。
「違うの!ポロって出ちゃって…」
私は言い訳するように言う。
「でも、良かったね。お母さん嬉しそうだった」
希望は、キッチンで洗い物をしている明君のお母さんに視線を向ける。
明君も、きっと、
私たちのようにいろんな思いを抱えて、
ここまで来たのだと思う。
母親のいない私には分からないけれど、
きっと、明君のお母さんだって、
耳が聞こえないことで、
明君が傷ついてないか、
明君が辛い思いをしていないか、
ずっと不安だったんだと思う。
母親に愛されている明君が、
なんだか少し羨ましかった。
「私……ちゃんと明君に気持ち伝えたいな……」
気づいたら、
そんなことを口走っていた。