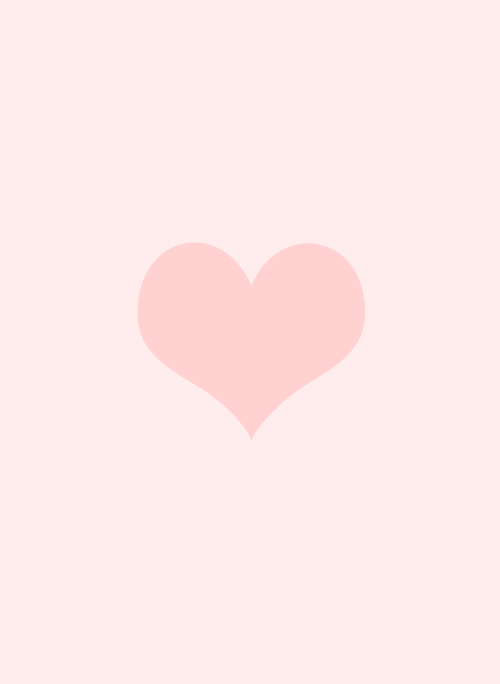ふいに景色が変わる。
伸ばされた手が観えなくなり、代わりに節くれだった手が現れた。
老いた人間特有の雰囲気を持つ、職人の手だ。
骨ばっているから男だろう。
とすると、今の思葉の視界はこの手の主のものだ。
大きな板の上で、灰汁色の粘土をしっかりと捏ね一つの塊にしていく。
やがてそれを今度は円形の板に載せた。
職人はその板の前に腰かけると、同じように年月を重ねた左足を下段の板に当てた。
蹴轆轤(けろくろ)だった。
現在は電動式の轆轤が一般的となっているから珍しい。
下段の円板が蹴られ、それに連動して粘土の載った板が時計回りに回り始める。
職人は椀に注いだ水で手を濡らし、回転する粘土に触れた。
柔らかい粘土はその通りに形を変えていく。
壺をつくっているのだろうか。
伝統工芸に限らず、何かをつくりだす作業過程を見るのは好きだ。
人の手が加えられることで、ただの材料があらゆる姿へと変化する。
その変化、そしてその先に完成するものを見届けるのは、おもしろくてわくわくする。
どんな形になるのだろう、どんな想いを込められるのだろう。