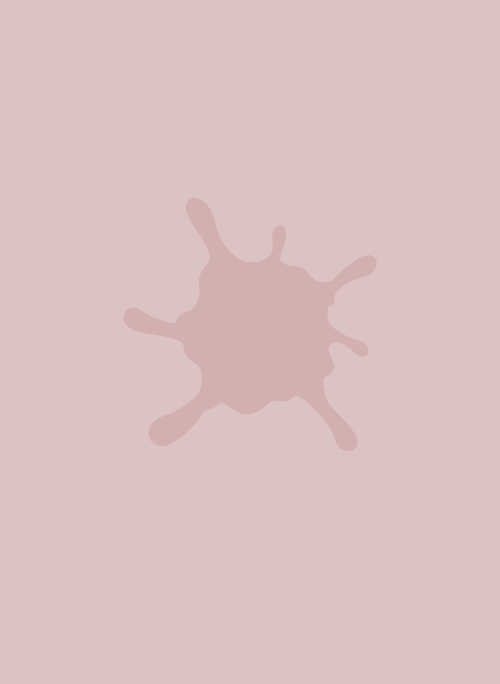「南條君」
私はできたてのお昼ご飯を片手に、
南條君の部屋をノックした。
「どうぞ」
中からいつもと変わらない声が聞こえた。
私はドアノブをひねると南條君の部屋にお邪魔する。
「お疲れ様〜」
「ん。さんきゅ」
コンクールまで1ヶ月を切った今では、南條君はろくに栄養のあるご飯を食べていない。
だから、私はこうしてよく差し入れに来ていた。
「お前も暇なんだな」
南條君がご飯に箸をつけながら言う。
「なんで?」
「毎日毎日俺に構って」
その言葉に、噴き出しそうになる。
そして、顔が真っ赤になっていくのを感じた。
「いや…なんでもない」
南條君はそう言って箸をすすめた。