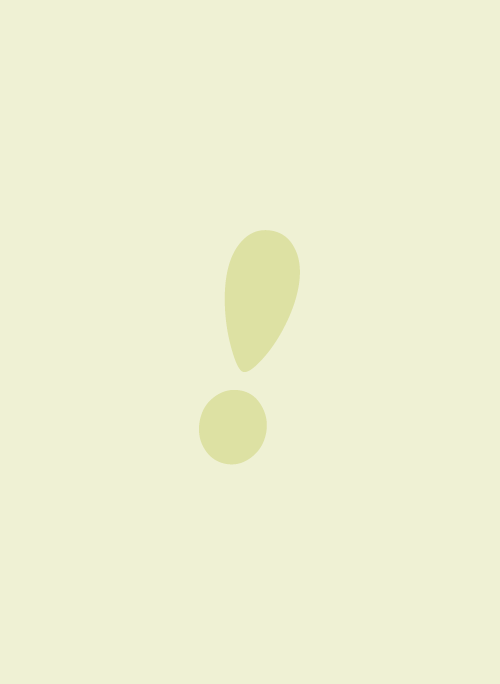社の裏の森の中、樹に隠れるように、男の子が立ってこちらを見ていたのだ。
「こんなところにいたら危ないよ」と声をかける猫目にも反応せず、じっとこちらの様子を伺っている。
「村の子供か……?」
小さく呟く朔に、銀花は静かに首を振ってみせる。
「違うわ。妖が化けているのよ」
「なぜわかる」
「なんとなくでわかるでしょ」
わかんねえよ、という言葉は飲み込んで、朔は刀の柄に手をかける。
銀花との約束なので斬りはしないが、いざというときにすぐに動けるように。
だが、警戒する朔と反対に、銀花は呑気なものだった。