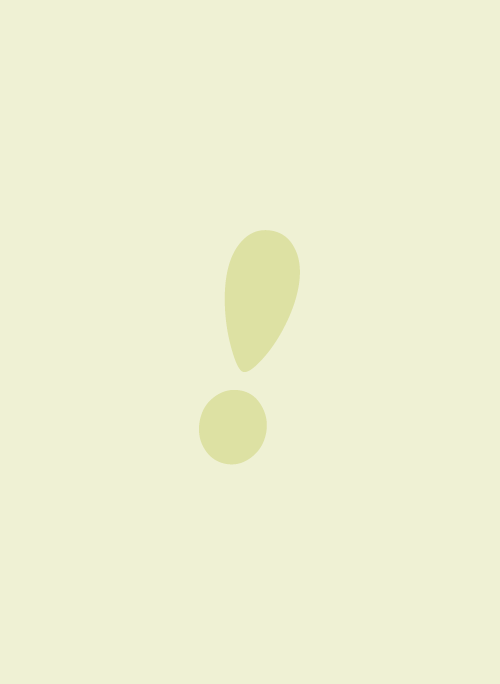腰にささった刀の柄を一度撫でて、朔は言う。
「だから、俺もついて行く。おまえが何をやらかすのかも気になるし」
やらかすって何よ、と思ったが、銀花は何も言わなかった。
これ以上ここで留まっていても仕方がない。
二人は猫目の後について、社の鳥居をくぐった。
賽銭箱もないような、本当に小さな何の変哲もない社だ。
本当に妖なんているのかしら、と銀花がそっと手を伸ばしたとき。
「あ、ねえ君!」
社の裏へ回っていた猫目が突然声を上げ、銀花は驚いて手を引いた。
「ど、どうしたの猫目?」
言いながら銀花は社の裏側へ回って、あ、と声を上げた。